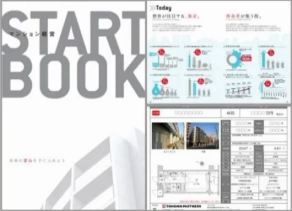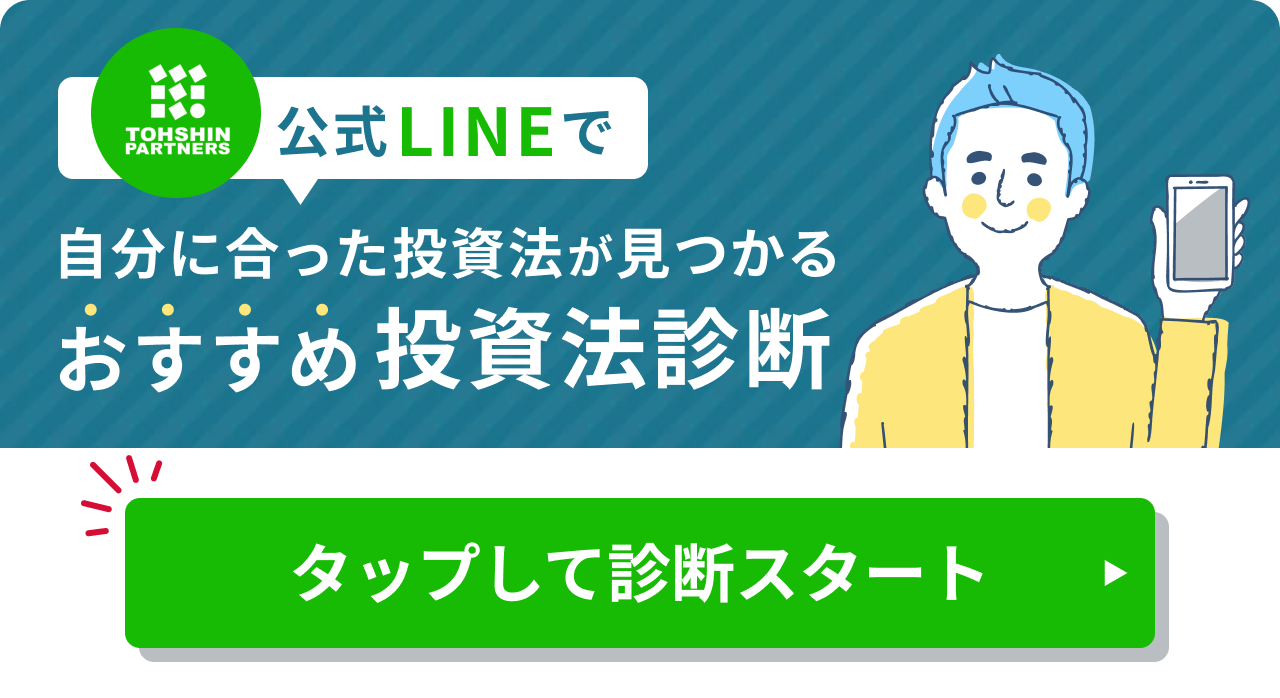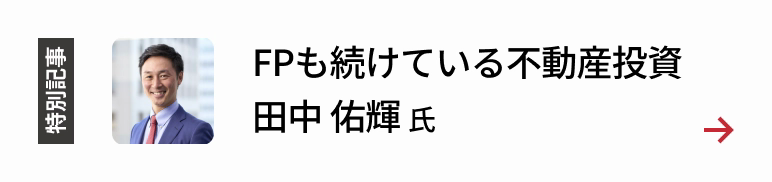- 不動産投資のリスク
不動産投資の失敗事例5選|事例から学ぶ失敗する人の特徴や対策も解説
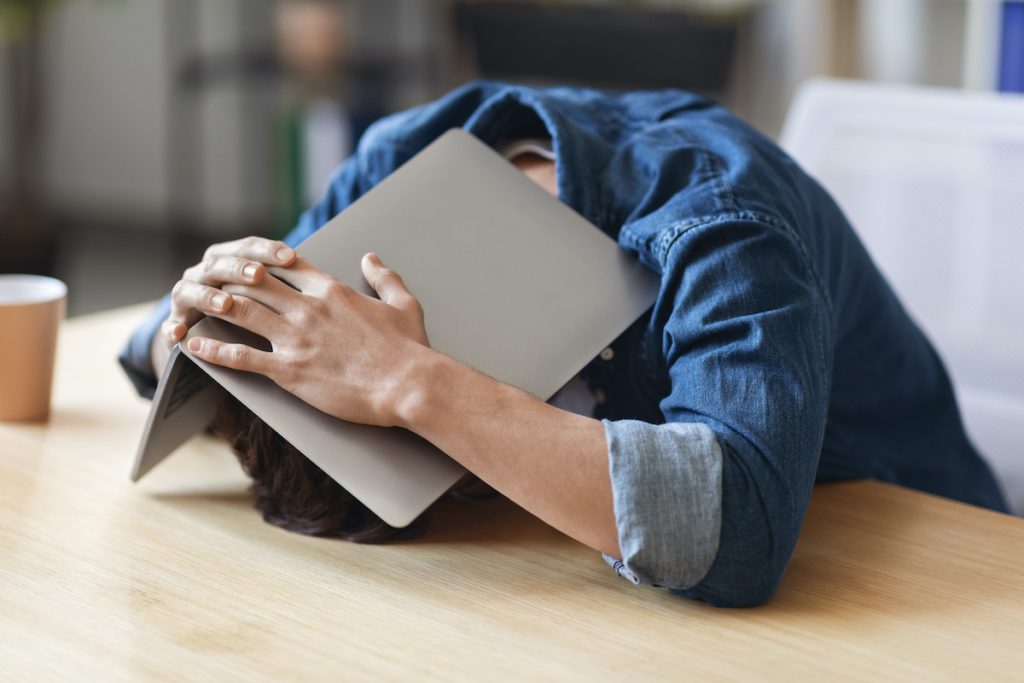
不動産投資は資産形成や安定収入を得る手段として人気ですが、一方でリスクも伴います。失敗を避けるためには、事例や成功のポイントを理解し、適切な対策を講じることが大切です。
この記事では、不動産投資の失敗率や失敗しやすいケース、成功のためのポイントを詳しく解説します。これから不動産投資を始めようとしている方や、すでに運用を始めた方にとって役立つ情報をお届けしますので、ぜひご一読ください。
不動産投資の失敗率
不動産投資の失敗率について、公的なデータは存在しません。しかし、「成功率10%、失敗率90%」といった数字が一般的に言われることがあります。ただし、これらの数字には統一された基準がないため、必ずしも正確とは言えません。不動産投資の「成功」や「失敗」の基準は人によって異なるからです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 成功の例:家賃収入が安定して得られており、投資を始めた目的を果たしている
- 失敗の例:空室が続き収益が上がらず、ローン返済が困難になる
また、不動産投資には単に「利益を出す」だけではなく、以下のような目的を持つ場合もあります。
- 家賃収入の確保:毎月安定した収入を得ることで、老後の資金や生活費を補填する
- 所得税の対策:減価償却を活用して、給与所得などの課税額を軽減する
- 相続税の対策:現金よりも不動産の方が相続税評価額を抑えられるため、相続時の税負担を軽減できる
このように、不動産投資の「成功」や「失敗」は、その人の目的や期待に応じて変わります。そのため、事前に自身の投資目的を明確にし、それに沿った計画を立てることが重要です。不動産投資の成功率、その他の投資の成功率については以下の記事をご覧ください。
不動産投資の成功率は?他の投資との比較や成功例・失敗しないコツも
初心者が陥りやすい不動産投資の失敗事例5選

不動産投資のリスクを把握して対策を考えるためにも、不動産投資の失敗事例を確認することは大切です。以下、初心者の陥りやすい不動産投資の失敗事例5選について見ていきましょう。
事例1:空室が埋まらない
「空室が埋まらず家賃収入が入らなくなった」という失敗は不動産投資でよくある問題です。一棟マンションやアパートなら1室の空室は致命的ではありませんが、ワンルームマンションなどでは家賃収入が0円となり、大きな打撃を受けます。
特に「目先の利回りに囚われて地方の安価な物件を購入したものの、入居者がつかずローン返済計画が崩れ、出費が増えたうえに売却も困難になった」というケースは珍しくありません。地方物件は利回りが高く見えますが、賃貸需要がなければ空室が続き、収益どころか負担が増すリスクがあります。
また、空室時の利回りやキャッシュフローを考えずに投資すると、家賃収入が途絶えた際に資金繰りが厳しくなります。家賃保証サービスを活用するなど、リスク分散の対策を講じることが重要です。
さらに、空室リスクを抑えるには、賃貸需要の高いエリアの物件を選び、適切な入居条件を設定することが不可欠です。不動産投資に空室リスクはつきものですが、事前の準備と対策によって影響を最小限に抑え。
事例2:自分で判断せずに管理会社などの意見をうのみにしてしまった
「管理会社の意見をうのみにしたら入居者満足度が下がり、空室が多くなった」「営業マンの話をすべて信じて物件を購入したら都合が良すぎる家賃設定になっており、入居者が集まらない」など、他人の意見を鵜呑みにして失敗するケースは少なくありません。
例えば、「よく調べずに管理会社を選んだところ、後々多額の修繕費を請求され、収支の計画が崩れてしまった」という事例があります。管理会社選びを慎重に行わなかったことで、想定外のコストが発生し、経営が厳しくなったケースです。
不動産投資では、自分で判断し、責任を持つことが重要です。数千万円もの物件を購入し、何十年も運営するため、他人の意見だけで決めてはいけません。たとえ失敗したとしても、責任を取るのは自分自身です。管理会社、不動産会社、友人、知人など、さまざまな人の意見を参考にするのは良いですが、全てをうのみにせず、自分でしっかり考えて判断することが大切です。
「◯◯の物件を購入した方が絶対に良い」「△△エリアの物件を購入すべき」「リフォーム内容は◯◯が良い」などのアドバイスを受けた際は、その背景や根拠を必ず確認しましょう。他人の意見はあくまで参考の一つとし、最終的な決断は自分自身の責任で行うことが、成功への鍵となります。
事例3:リスク管理・予測ができなかった
リスク管理や予測が甘かったことが原因で、不動産投資に失敗するケースは少なくありません。
- 悪質な入居者が入り、家賃を滞納する上に部屋の中を傷だらけにした
- 物件を購入して1年足らずで大規模修繕が実施され、多額の費用がかかった
- 家賃下落や金利上昇のリスクを考えきれておらず、採算を取るのが難しくなった
- 所有物件の周辺に競合物件が増え、想定以上に空室が発生した
- 管理費が月1,100円の安さで物件の管理会社を選んだが、途中で大幅な値上げをされてしまった
特に、管理費の安さを理由に管理会社を選んだ結果、後から大幅な値上げが発生し、収支計画が狂ってしまうケースもあります。初期費用の安さだけで判断すると、長期的なコスト増につながるリスクがあるため、慎重な見極めが必要です。
不動産投資には多くのリスクがあるため、事前に対策を考えた上で物件選びや運営を行うことが重要です。リスク管理や予測が甘ければ、実際にトラブルが発生した際に適切な対応ができず、多額の損失につながる可能性があります。不動産投資にどのようなリスクがあるのかを把握し、過去の失敗事例に学びながら、リスク回避の計画を立てることで、成功する確率を高められるでしょう。
事例4:運用目的を忘れて自分に適さない物件を購入してしまった
不動産投資の目的に適さない物件を購入したことで、失敗するケースも多いです。
- 老後の年金代わりを目的としていたが、価格が安いという理由だけで購入してしまい、賃貸条件の悪さから空室率が高くなり、失敗した
- 10年運用してからの売却を考えていたが、人口減少が続く地域の物件を選び、資産価値が下がり続けていて売却益が期待できない
- 年間50万円の利益を目的としていたが、新しい競合物件がいくつもでき、家賃の値下げ合戦が始まり、利益が半分くらいしかない
不動産投資で大事なのは、明確な目的を決め、実現のための計画を立て、実行していくことです。検証や軌道修正をしやすく、成功へ近づくことができます。目的を決めても忘れてしまったり、方向性の違うことをしたりしていては、計画的な運営はできません。目的や計画に合った物件を購入しましょう。
事例5:ローンを組んだ際の返済プランが甘い
ローンを組んだ際の返済プランが甘いことで、失敗するケースも多いです。
- ローンを組んで購入したが、月々の返済額が多く、空室時に返済が滞ってしまった
- 借入金額が多く、金利も高いため、総支払い金額が膨らんでしまい、利益を出しにくい状況を生んでしまった
- 「なんとか返済できるだろう」と返済期間を短めに組みすぎて、月々の返済額が高く、支出が多くなってしまう
ローンを組む前に、厳しめのシミュレーションを行うことが大切です。見通しの甘い返済プランだとリスクが高いため、気を付けましょう。
事例から学ぶ不動産投資を失敗する人の特徴
不動産投資で失敗する人には、共通する特徴があります。これらの特徴を知り、回避するための対策を把握することが成功への近道です。不動産投資を失敗しやすい人の特徴は次の通りです。
- 計画性がない人
- 他人任せにしてしまう人
- リスク管理が甘い人
- 目的が曖昧な人
- 返済計画が甘い人
これらの特徴を持つ人が失敗しやすい理由は、それぞれ次の通りです。
計画性がない人は空室リスクや修繕費用など、予測できる問題に対する準備が不足しており、突発的な支出や収益の減少に対応できなくなることがあります。他人任せにしてしまう人は、管理会社や営業マンの意見を鵜呑みにし、自分で判断を行わないため、採算が取れない物件を購入するリスクが高まるでしょう。
また、リスク管理が甘い人は家賃下落や金利上昇、空室リスクなどを想定していないため、問題が発生した際に迅速な対応ができず、損失が拡大してしまいます。さらに、目的が曖昧な人は、不動産投資の目標が定まっておらず、購入した物件が自分の目的に合わず、期待する成果を得られない場合があるでしょう。
最後に、返済計画が甘い人はローン返済のシミュレーションが不十分で、収益減少や空室時に返済が滞るリスクが高く、経営が悪化してしまいます。
これらの失敗の特徴に共通するのは、「準備不足」「リスク管理の甘さ」「自主的な判断力の欠如」です。不動産投資で成功するためには、これらの弱点を克服し、事前に計画を立てて目的に沿った投資を心がけることが重要です。
不動産投資で失敗しないためのポイント

周辺相場や物件価値を念入りに調査するなど、不動産投資で失敗しないためのポイントを把握しておくことは大切です。失敗しないためのポイントを知っていると、失敗するリスクを抑え、成功確率を上げることができます。以下、不動産投資で失敗しないためのポイントについて紹介します。
| 【不動産投資で失敗しないためのポイント】 |
|---|
| ・周辺相場、物件価値を念入りに調査してから購入する |
| ・不動産投資によって何を得たいかを決めてから始める |
| ・短期間で大きなリターンを求めない |
周辺相場や物件価値を念入りに調査してから購入する
不動産投資を成功させるためには、周辺相場や物件価値を念入りに調査してから購入しましょう。周辺相場や物件価値を調査していれば、相場よりも割高な物件の購入を回避することができます。相場よりも割安な物件を購入できれば、利益の出る可能性が上がります。逆に、相場よりも割高な物件を購入してしまうと、損益分岐点が高くなるため、損する可能性が上がるでしょう。
周辺相場や物件価値を調べる方法は、以下の通りです。
- 土地総合情報システムで調べる
- レインズ・マーケット・インフォメーションで調べる
- 不動産情報ポータルサイトで調べる
- 不動産会社に聞く
どの方法も、お金をかけずに調べることができます。一つの方法にこだわらず、複数の方法で多角的に調査することが大切です。「少しでも割安な物件を購入したい」「条件の良い物件を選びたい」という人は、時間をかけて調査した上で物件を購入してください。
不動産投資によって何を得たいかを決めてから始める
不動産投資を始める際は、「不動産投資によって何を得たいのか」などといった目的をはっきりとさせておくことが大切です。目的が明確であれば、目的を達成するための具体的な計画や対策を立てやすくなります。判断基準ができるため、決断する際に悩むことが少なくなります。また、目的に正解はないため、人と異なる内容でも問題ありません。
- 毎月2万円以上の利益を得る
- 10年間運用して500万円以上の利益を得て売却する
- 定年までにローンを完済し、家賃収入を私的年金代わりにする
- 積極的に繰上返済を行い、ローンを減らして10年以内にもう1物件購入する
- 年間50万円以上の利益を出して家計に余裕を持たせる
以上のように、自分なりに不動産投資を始める目的を決めた上で始めるようにしましょう。
短期間で大きなリターンを求めない
不動産投資で失敗しないためのポイントは、短期間で大きなリターンを求めないことです。不動産投資は、FXや株式投資とは違い、常に価格が変動しているわけではありません。不動産投資の相場は、その土地の評価額が基準となるため、相場から大きく外れた取引をするのは難しいです。
また、短期間で物件価格が上昇したことによる売却益を期待できる物件はほとんどありません。購入時点から急激に資産価値が上がるような物件と出会えることはまれであり、狙って購入できるものではありません。経験豊富な不動産投資家であればまだしも、投資初心者が短期間で大きなリターンを狙うのは危険です。
あくまでも家賃収入で収益を出すことを考えた物件選びや運営をおすすめします。
失敗しないためにはデメリットを把握しておくことも重要

不動産投資で失敗しないためには、デメリットも把握しておくことが重要です。「物件選びが大変」「売却を希望する時期に売却できない可能性がある」など、不動産投資のデメリットがわかると、投資していく中で注意すべき点が明確になり、リスク対策を講じやすくなります。できるだけ多くの失敗事例とデメリットを把握し、失敗する確率を下げましょう。
ここでは、失敗しないために把握しておきたい不動産投資のデメリットについて紹介します。
さまざまなリスクが発生しやすい
不動産投資のデメリットは、さまざまなリスクが発生しやすいことです。不動産投資には、次のようなリスクがあります。
- 空室リスク
- 滞納リスク
- 家賃下落リスク
- 金利上昇リスク
- 修繕リスク
- 災害リスク
- 価格下落リスク
どのリスクも発生する可能性があり、修繕リスク、金利上昇リスク、災害リスクなど、予測が立てにくいリスクもあるため、注意が必要です。例えば、空室リスクや滞納リスクが発生すると、家賃収入が入らなくなります。金利上昇リスク、修繕リスク、災害リスクが発生した場合は、月々の返済負担が増えたり、まとまった費用が発生したりします。不動産投資は、さまざまなリスクが発生しやすいことを理解し、事前に対策を考え、講じておくことが大切です。
物件選びが大変
不動産投資の成否を分ける重要なポイントとなるのは、物件選びです。「立地が良い」「賃貸需要が高い」など、条件の良い物件選びができれば、不動産投資の成功率は高くなります。反対に「立地が悪い」「利回りが極端に高い」など、条件の悪い物件を買うと、不動産投資の失敗率が上がります。しかし、条件の良い物件選びは、簡単なことではありません。次のような物件は、買わないようにしましょう。
- 駅、バス停から遠い
- 想定利回りが極端に高い
- 管理が杜撰
- 周辺物件の空室率が高い
- 近くにスーパーマーケット、コンビニエンスストアがない
上記のような物件は、賃貸需要が見込めない可能性があります。物件を選ぶ際は、駅やスーパーマーケットなどが近く、利便性の高い物件を選びましょう。
売却を希望する時期に売却できない可能性がある
不動産投資は、必ずしも希望の時期に売却できるというわけではありません。売却を希望していても、買い主が見つからなければ売買は成立しないからです。売りに出して売却が決まるまでには、1年以上かかることもあります。そのため、「半年以内にまとまった資金が必要なので、売却したい」と考えていても、実現できない可能性があります。売却時期が遅くなると、維持費がかかるだけでなく、売却金額を下げるなどの対処が必要です。
不動産は金額が大きいため、購入時・売却時のどちらの場合でも、簡単に売買が成立するものではありません。希望時期に売買できない可能性があることを理解し、計画を立てる必要があります。
物件の維持が大変
不動産投資は、物件の維持管理が大変であることもデメリットです。物件の維持管理に必要な対応には、次のようなものがあります。
- 建物の屋根、外壁の修繕
- フローリング、壁紙の修繕
- キッチンなどの設備の修繕、買い替え
上記の他にも、さまざまな維持管理が予測できないタイミングで発生し、その都度まとまった費用がかかります。物件の維持管理をないがしろにすると、入居者の満足度が下がり、空室リスクが高くなります。また、資産価値の下落や物件の安全性能の低下につながるため、注意が必要です。不動産投資は、物件の維持管理が大変なことを理解し、維持管理に関する長期の計画を立てておくことが大切です。
固定資産税がかかる
不動産投資のデメリットは、固定資産税がかかることです。固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を所有している方にかかる税金です。
固定資産税の対象となる資産には、宅地、田、畑、物置、車庫、倉庫などがあります。不動産投資で一棟マンション、一棟アパート、ワンルームマンションなどを所有している場合においても、固定資産税がかかります。納税先は、固定資産が所在する市町村(または都)です。固定資産税は、固定資産税評価額をもとにした「課税標準額」に一定の税率を掛けて算出されるため、地価の高いエリアほど税額は高くなる傾向にあります。マンションやアパートなどの不動産を所有していると、毎年固定資産税を負担しなければなりません。
「不動産投資はやめとけ」と言われる理由は?本当にリスクが高いのかを徹底検証!
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
不動産投資のよくある質問(FAQ)まとめ
Q.不動産投資はいくらから始められる?
A.不動産投資に必要な費用はどのような不動産を選択するかによって異なります。例えば、中古区分マンション投資や戸建投資は投資規模が小さいですが、アパート投資や複数の物件を運用する場合には投資規模が大きいので多額の資金が必要です。
不動産投資にかかる初期費用は物件価格の15%程度と言われているため、投資規模に合わせて必要な初期費用を算出してみましょう。
Q.不動産投資は少額でもできる?
A.金融機関によっては初期費用を含むフルローンを組めるため、自己資金がない人でも不動産投資を始めることは可能です。しかし、借入額が大きくなると、金利の影響を受けやすい、返済計画に支障が生じやすくなるため、不動産投資のリスクが高まります。不動産投資のリスクを抑えるためにも、物件価格の15%程度の自己資金を用意しておきましょう。
Q.不動産投資の理想の利回りは?
A.不動産投資の利回りは、運用する物件によって大きく異なります。例えば、新築物件や都心の物件は利回りが低く、中古物件や郊外の物件は利回りが高くなります。条件が良い物件であるにもかかわらず、利回りが高い物件は何らかの問題が潜んでいる可能性が高いため、3~7%程度を1つの目安にすると良いでしょう。
Q.不動産投資と株式投資の違いは?
A.両者の大きな違いは、収益構造です。不動産投資は資産を保有することで得られる賃料収入(インカムゲイン)がメインですが、株式投資は資産を売却することで得られる売却益(キャピタルゲイン)がメインです。株式投資は短期で大きな利益を狙える一方、価格変動を予想するのが難しいため、利益を得ることは容易ではありません。
不動産投資は短期で価格が大きく変動することはほとんどなく、比較的安定的に収入が得られます。そのため、短期的な大きな収入を得たい人は株式投資、長期的に安定した収入を得たい人は不動産投資が向いていると言えるでしょう。
Q.人口が減少するなかで将来的に賃貸需要はあるのでしょうか?
A.東京、特に都心部では需要が供給を上回っているのが現状です。東京都の単独世帯数は2020年時点で339万世帯、2040年に至っては369万世帯まで増加が予想されているにも関わらず、一方で1988年から2021年までの首都圏の投資用マンションの発売戸数は187,397戸です。このことから単身者向けマンションのユーザーニーズは年々高まっていくと考えられています。
Q.管理とは具体的に何をすればよいのですか?
A.自分で管理をする場合、入居者の募集や家賃の集金、賃貸契約や建物のメンテナンスまで様々な業務が発生します。ただし専門の管理会社に業務を委託することができるため、管理業務に時間を取られることはなく、知識や経験も不要です。ちなみに25平米程度の1Kタイプの物件で、4~5,000円前後の手数料が一般的です。
Q.家賃が下がりにくいマンションの特徴は?
A.住む人の目線でつくられています。実用性、安全性など設備やその性能が優れていることはもちろん、働き方の多様化に伴い、自分らしい暮らしができる間取りやデザインの部屋が求められるようになりました。住む人にとって価値を感じられない部屋は家賃を下げなければ入居者に選ばれることはなくなってきています。
Q.マンションに寿命はありますか?
A.マンションにも寿命はあります。鉄筋コンクリート造のマンションの場合、財務省で定められた法定耐用年数(固定資産評価や税制上の減価償却年数)は47年とされています。 しかし、これはあくまでも法定の耐用年数であり、物理的な『寿命』とは異なります。定期的な補修をおこなうことで100年持たせることも可能と言われており、綿密な修繕計画が寿命を左右します。
Q.空室リスクを避けられる物件は?
A.需要が高く、供給が少ない立地の物件です。一般的に需要が高いとされる人気のエリアは交通の利便性が高い傾向にあります。ワンルームマンションの借り手は圧倒的に若年層が多く、通勤やプライベートを楽しむ場所の近くに住むことを好むからです。また駅から徒歩10分圏内であれば便利なだけでなく、新しい物件を供給できる空地は少ないため新しい物件に入居者が流れにくくなります。市区町村によってはワンルームマンションの供給を規制する条例があるためそのような立地を選ぶことも重要です。
Q.空室になった場合はどうなりますか?
A.家賃収入を得られないため、ローンの返済や管理コストを自己資金から賄う必要があります。退去が決まった時点から賃貸募集を開始しますが、人気の物件であればすぐに次の入居者が決まるため、長期で空室になることは滅多にありません。管理会社によっては、入居者の有無にかかわらず管理会社から直接家賃を得られる保証サービスを用意しています。空室リスクが気になる場合は家賃保証サービスの利用を検討すると良いでしょう。
Q.ローンが残っていても売却することはできますか?
A.可能です。特にワンルームマンションの場合は投資として市場が形成されており、売買双方の需要が豊富だからです。もし売却時にローンが残っていても、売却によって得られる現金で一括返済することができます。また家賃収入でローン返済を行っていけば自ずと投じる自己資金が少なくなるため、購入価格よりも値下がりしても売却によって利益を得ることが可能です。
Q.会社が倒産したらどうなりますか?
A.購入後、お引渡しをした時点で所有権は売主からオーナー様に移転しており、個人の財産なので販売会社の倒産は全く関係なく、実物資産として保有し続けられます。
Q.購入される方はどのような方が多いですか?
A.会社員、会社役員、公務員、医師など職業は様々です。年代は20代から70代以上まで幅広く、30代・40代がボリュームゾーン。ほとんどの方がローンで購入されるため、個人年収は500万円以上の方がほとんどです。一方で目的やプランは資産形成や分散投資、生命保険がわりに保有されるなど十人十色です。
Q.マンションを維持するにはどのようなコストがかかりますか?
A.一般的に「外壁補修や給水管補修、屋上の防水補修に費用など共有部分のコストと入退去時のリフォームや原状回復費用など専有部分のコストが発生します。共有部分のコストは、所有者から集める積立金で賄い、マンションのグレードによって違いがでますが、現在は建築資材の品質が向上しており、ほとんど修繕を必要としないものもあります。また、専有部分のコストは別負担となりますが、オーナー負担の部分と入居者が負担する部分で按分されます。
Q.マンションの資産価値が下落することはありますか?
A.資産価値は一定ではなく、ゆるやかに変動するため上昇することもあれば低下することもあります。新しくても借り手が付かない物件は家賃が下がりやすく資産価値は下落する可能性が高くなり、逆に築年数が経過しても賃貸需要が高い物件は家賃が下がらないため、資産価値は維持されます。
まとめ

不動産投資は、長期的な資産形成や安定収入などを目指すための有力な手段ですが、リスクを正しく理解しないまま始めると失敗の原因となります。
初心者が陥りやすい失敗には、空室リスクや返済計画の甘さ、物件選びのミスなどがありますが、これらは事前の準備と計画で回避可能です。また、不動産投資を成功させるためには、目的を明確にし、周辺相場や物件価値などをしっかり調査することが重要です。短期間での利益を狙わず、安定した家賃収入を重視した運用を心がけることで、ローリスクで長期的なリターンを得ることができます。
不動産投資を始める際には、今回ご紹介した情報を参考に、慎重に計画を立ててください。