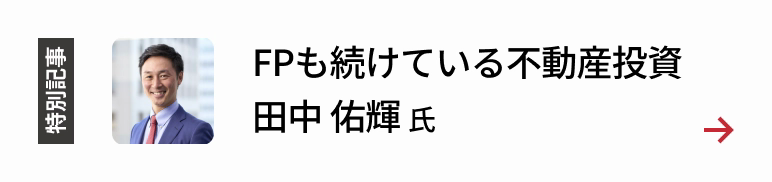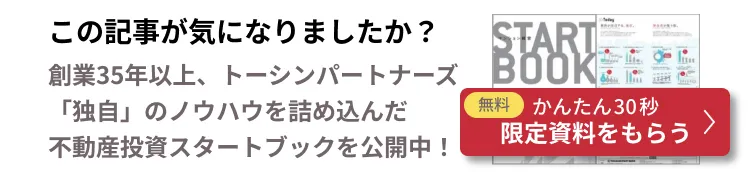- 不動産投資のメリット
個人ができる節税対策14選!会社員・個人事業主におすすめの方法を解説

商品を購入したり給与所得を得たり、金銭を受け取る際には国が定めた税金を支払わなければなりません。適切な手続きを行えば節税ができるものの、どのような方法があるのかわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、個人でも実践できる節税対策を10パターンに分けて徹底解説します。取り組みやすい方法を選ぶことにより、節税を効果的に行えるでしょう。後半では個人事業主に適した4つの節税対策もご紹介します。
節税対策とは?

節税対策とは、租税に関する法令に規定されたルールの範囲内で、税金の支払いを少なくするための対策をいいます。節税対策は、支払わなくても済むはずの税金の負担を避けるために行うものです。
基本的に税務署が節税対策を教えてくれることはありません。個人事業主や会社員ができるだけ手元にお金を残すには、税に関する正しい知識を持って、節税対策に取り組む必要があります。
サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選|少しの手間で手取りを増やす方法
もぜひチェックしてみてください!
個人や会社員におすすめ!節税対策のおすすめ10選

節税対策として実践できる方法は、個人年金やふるさと納税を利用するだけでなく、控除を上手に活用するなどさまざまです。それぞれの特徴や仕組みを理解して、自分が始めやすい節税対策を選択しましょう。10パターンの方法を項目に分けて詳しく解説します。
- 個人年金を利用する
- 生命保険を利用する
- 不動産投資を行う
- iDecoを利用する
- NISAを利用する
- ふるさと納税を利用する
- 両親を扶養家族にする
- 医療費控除を活用する
- 住宅ローン控除を活用する
- 特定支出控除を活用する
個人年金と生命保険は、それぞれ生命保険料控除の枠を利用して所得控除が受けられます。不動産投資は、不動産の減価償却を利用することで不動産所得を減少させ、節税につながる方法です。また、相続税対策としても活用できます。iDecoとNISAは混同されることがありますが、給与所得や事業所得の節税になるのはiDeCoの方です。一方、NISAは運用益が非課税になる制度です。ふるさと納税を活用すると、自己負担2,000円で各地の自治体から返礼品を受け取ることができます両親を扶養に入れると、所得税・住民税の節税にはつながりますが、両親の医療費や介護サービス利用料の負担が増える可能性がある点に注意が必要です。医療費控除の適用を受けられる場合は、セルフメディケーション税制といずれかの選択となります。マイホームを購入した際には、住宅ローン控除の適用対象になる場合は、所得税などの負担を大幅に減らせます。仕事関連の支出が多い場合は、特定支出控除を活用できる可能性があります。
個人年金を利用する
個人年金は国が定める国民年金保険制度とは別で、任意の年金保険に加入する方法です。複数の種類に細分化すると、以下のような個人年金が選択できます。
- 確定年金:一定期間年金の受け取りが可能
- 有期年金:被保険者が生存しているあいだ、一定期間受け取りが可能
- 終身年金:被保険者が生存しているあいだ、無期限で受け取りが可能
- 変額個人年金:保険会社の運用実績にともなって年金額が変動
加入する年金保険の種類によって異なるのは、「被保険者の生存期間中にどのくらいの年金を受け取れるか」という点です。
個人年金を利用すると、生命保険料控除の「新個人年金保険料控除」の区分の適用を受けられます。課税対象の所得金額や住民税から差し引くかたちになるため、会社員の節税対策にも有効です。適用には以下の条件がある点も把握しておきましょう。
- 契約者または配偶者が受取人で保証対象人物
- 支払い期間が10年以上
- 原則満60歳以上に支払われる定期年金・終身年金
●メリット
- コツコツと老後のための資産形成を図れる
- 生命保険・介護医療保険と別枠で、所得税・住民税の所得控除を受けられる
●デメリット
- 所得控除額が所得税で最高で4万円と少ない
- 老後資金対策ではiDeCoの方が節税効果が高い
【個人年金がおすすめな人】
- 老後の資金対策をしたい人
- プロに運用を任せたい人
個人年金は、節税と老後資金の準備を兼ねたい人に向いています。ただし、全額掛金が所得控除できるiDeCoの方が節税対策としては有利です。したがって、プロに運用を任せたい人に向いています。
生命保険を利用する
生命保険に加入する選択肢も、課税対象の所得税や住民税を抑える方法のひとつです。生命保険料控除の「新生命保険料控除」の区分で適用を受けられます。
控除可能な金額には上限が設けられているため、「保険料が高額なほどお得になる」というものではありません。
場合によっては出費が増幅する可能性もあります。生命保険料控除で節税対策を行う場合は、月間・年間でどのくらい節約できるのかシミュレーションできると安心です。生命保険の加入プランも細かく確認しながら決断しましょう。
また、2012年1月1日前後の加入時期では取り扱いや条件も異なります。これから加入する場合は新制度のルールが適用されるため、控除制度が活用できるかを考慮しながら決めましょう。
年金だけでは安心できない方に読んでほしい、不動産投資スタートブックの無料プレゼントはこちら
●メリット
- 個人年金保険・介護医療保険と別枠で、所得税・住民税の所得控除を受けられる
- 相続税対策も兼ねられる
- 万が一のときに家族にお金を残せる
●デメリット
- 所得控除額が所得税で最高で4万円と少ない
- 長期にわたって保険料を払い続ける必要がある
【生命保険がおすすめな人】
- 扶養する家族がいる人
- 相続税対策をしたい人
扶養する家族がいる人は、多くの資産を持っている場合を除き、生命保険に加入し、万が一に備えておく必要性が高いです。また、生命保険の保険金には相続税の非課税限度額が設けられているため、相続税対策を考えている人にもおすすめです。
不動産投資を行う
投資方法のひとつとしても知られる不動産投資は、個人や会社員の節税対策に有効な方法です。一例ですが、以下の項目を申告することで税務上赤字になると、給与所得や事業所得との損益通算により、節税が可能です。
- 不動産取得税
- 修繕費
- 火災保険や地震保険
- 減価償却費
課税所得のみならず、取得時に税金が抑えられる点もメリットといえるでしょう。法定耐用年数を迎えるまでの期間であれば、減価償却費を反映することでさらなる節税効果が期待できます。国で定められている減価償却費は、建物の構造と用途によって区分される仕組みです。
また、大規模な投資において法人化した場合、法人税適用による節税効果が得られる点も認識しておきましょう。資産形成を実現するだけではなく、継続的に税金を節約しやすい選択肢です。
●メリット
- 投資方法の中で比較的手間がかからない
- 投資物件の選び方によっては、所得税・住民税の節税効果が大きい
●デメリット
- 購入から売却までの収支を考える必要がある
- 減価償却費を差し引ける期間を過ぎると、節税効果が薄れ、売却も難しくなる
【不動産投資がおすすめな人】
- 課税所得が900万円を超える人
- 相続税対策も兼ねたい人
不動産投資による節税は課税所得が900万円を超える人に向いているのは、所得税は超過累進税率が適用されているため、課税所得900万円を超える人は節税効果が高いためです。また、ローンが組みやすいほか、不動産投資にはランニングコストがかかり、大規模修繕工事の費用なども負担できる財力があることも理由に挙げられます。
また、資産を現金よりも、不動産として持つ方が相続税評価額を抑えられることから、相続税対策を兼ねたい人にも向いています。
iDecoを利用する
個人年金保険とは異なり、証券会社にお金を預けて運用するのがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。証券会社が設定した限度額内で積み立てを行い、自分で運用しながら貯蓄額を増やしていきます。
対象となる控除制度は「小規模企業共済等掛金控除」です。個人事業主や会社員・公務員、専業主婦(夫)などの加入区分に応じて掛金の限度額が決められ、全額所得控除を受けられます。年金を受け取る際にも、受け取った金額に対しても控除が適用される仕組みです。
●メリット
- 運用次第で資産を増やせる
- 掛金に上限は設けられているが、所得税・住民税の全額所得控除の対象で、運用益も非課税
●デメリット
- 自分で金融商品を選択するため、運用の成果を上げるには知識が必要
- 運用によっては元本割れする可能性がある
【iDeCoがおすすめな人】
- 余剰資金がある人
- 老後資金を形成したい人
iDeCoは原則として60歳までは資金を引き出すことができないため、貯めたお金を途中で引き出して、マイホーム資金や教育資金などに充てるといったことができません。資金にゆとりがあり、老後資金を形成したい人に向いています。
NISAを利用する
主に個人投資家の節税対策に活用できる手段として、2014年1月に「NISA」が開始されました。専用のNISA口座を開設し、預けたお金を運用します。通常であれば利益に対して所得税がかかりますが、NISA口座内の一定額までであれば非課税対象になる仕組みです。
非課税対象の金額と期間を明確にしたうえで運用できると、税金を抑えながら満足な売買取引を続けられるでしょう。ただし、購入可能な金融商品に条件がある点も理解しなければなりません。
投資に不安を感じる方には、少額からスタートできる「つみたて投資枠」の活用がおすすめです。理想どおりに運用できれば、資産を増やしながら節税対策も実現できます。
●メリット
- 運用益が非課税
- 18歳以上なら誰でも利用できる
●デメリット
- 給与所得や事業所得の所得税・住民税の節税にはならない
- 元本割れする可能性がある
- 他の証券口座との損益通算ができない
【NISAがおすすめな人】
- 運用益にかかる税金を抑えたい人
- 必要なときに資金を引き出したい人
NISAはiDeCoと異なり、運用益に対する税金が非課税になる制度です。いつでも、金融商品を売却して資金を引き出せるため、運用したお金を様々な用途に活用できます。
ふるさと納税を利用する
近年注目される機会が多い「ふるさと納税」も、税金の節約につながる方法です。支払ったお金は「寄付」として扱われ、2,000円以上の部分が控除の対象となります。所得税・住民税を控除することで節税効果が得られる仕組みです。
入手が難しい特産物や工芸品など、返礼品を受け取れる点はふるさと納税ならではの魅力です。返礼品の内容を基準に選択できるため、節税効果とは別の要素でもお得感を得られるでしょう。控除対象の上限は所得や家族構成などによって変わります。
●メリット
- 寄附先を選んで返礼品を受け取れる
- 寄附金の使い道を指定できる
●デメリット
- 控除上限額を超えた分は控除されない
- 実際に負担する税金が減るわけではない
【ふるさと納税がおすすめな人】
- 各地の自治体の返礼品を楽しみたい人
- 応援したい自治体がある人
ふるさと納税では、自治体ごとにさまざまな返礼品が用意されているため、実質2,000円の負担で各地の返礼品を楽しみたい人に向いています。また、応援したい自治体がある人は、本来の趣旨に沿った形で制度を活用できます。
不動産投資でできる税金対策とは?3つの節税をどこよりも詳しく解説!
もぜひチェックしてみてください!
両親を扶養家族にする
年間所得金額が一定以下の親族がいる場合、扶養に入れることで税金の控除適用が可能です。同居している方だけではなく、仕送りを行っている場合も対象となります。控除額は親族の年齢によって異なるため、以下を参考に該当する金額を把握しておきましょう。
- 16歳以上の控除対象扶養親族:38万円
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族:63万円
- 70歳以上の同居老親など:58万円
- 70歳以上の同居老親以外:48万円
参考:『国税庁 扶養控除』
本気の節税対策を考えたくなる、30年以上の不動産投資ノウハウが詰まった無料資料請求はこちら
●メリット
- 健康保険の扶養にも入る場合は、親の保険料の負担を軽減できる
- 所得税・住民税の負担を減らせる
●デメリット
- 両親の医療費の負担が増える可能性がある
- 両親の介護保険料が高くなる恐れがある
- 両親の介護サービス利用料が増える可能性がある
【両親を扶養家族にする方法がおすすめな人】
- 両親の収入が一定以下の人
両親を扶養家族にできるのは、両親の収入が一定以下のケースです。ただし、両親の医療費や介護サービス利用料の負担の増加が、扶養に入れたことによる節税効果を上回るケースもあるため、シミュレーションをしてみることが大切です。
医療費控除を活用する
1月1日~12月31日に支払った医療費が高額な場合、医療費控除を適用することで節税効果が得られます。加入している保険から支給された金額も反映する必要があるため、以下の計算式を参考に控除額を算出しましょう。
- 1年間に支払った医療費-保険から支給された金額=A
- A-10万円=控除額
控除される金額の上限は200万円です。ただし、1年間の総所得金額が200万円を下回る場合は、所得に対して5%の金額が適用されます。美容目的の医療は控除対象外となるため注意が必要です。
自身や配偶者だけではなく、医療費を支払った生計を一にする親族がいる場合はすべて対象になります。控除を受けるには確定申告が必要となるため、医療費を明確にしたうえで手続きの準備を始めましょう。
●メリット
- 所得税・住民税の節税になる
●デメリット
- 確定申告の手間がかかる
- 原則として医療費が10万円を超えた分のみしか適用を受けられない
- セルフメディケーション税制と併用できない
【医療費控除がおすすめな人】
- 自分や家族が年間10万円を超える医療費を負担している人
- セルフメディケーション税制よりもお得な人
自分や家族が高額な医療費を負担している場合、確定申告で医療費控除の適用を受けることをおすすめします。ただし、セルフメディケーション税制の方が有利なケースもあるため、双方を比較計算したうえで、いずれかを選ぶことが重要です。
住宅ローン控除を活用する
ローン契約で住宅を購入した場合は「住宅借入金等特別控除」が適用されます。新築物件の購入だけではなく、増改築も控除の対象です。適用条件が設けられているため、あてはまるかどうかチェックしておきましょう。
<主な新築住宅の適用要件>
- 適用される年の12月31日まで居住している
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
- 床面積50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下で、2024年末までに建築確認を受けた場合は、40平方メートル以上に緩和)
- 床面積2分の1以上が居住用
- 10年以上の分割払い
- 一定期間、ほかの特例を受けていない
2024年以降の入居は、新築住宅は省エネ基準に適合していなければ、適用を受けられません。(例外あり)
1年間の所得が合計3,000万円を上回る場合は控除を受けられません。10年以上のローン契約も条件にあげられるため、すでに支払いを開始している方は契約内容を確認してみましょう。マイホームを手に入れたあとの負担を軽減できる方法です。
参考:『国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)』
●メリット
- 所得税が大幅に軽減され、所得税から控除しきれない場合には住民税からの一部控除を受けられる
●デメリット
- 1年目の利用時は会社員・公務員も確定申告が必要
- 適用対象外の住宅がある
【住宅ローン控除がおすすめな人】
- ローンを利用して、マイホームの購入・リフォームをした人
住宅ローン控除は、所得税などの負担が大幅に軽減されるため、適用の対象となる場合は、制度の利用がおすすめです。
特定支出控除を活用する
給与所得の控除額を基準とし、半額以上の特定支出があった場合に「特定支出控除」が適用されます(2020年4月21日現在)。
特定支出の代表例
- 通勤費:出社・退社に必要な交通費
- 転居費:転勤の際に必要な引っ越しなどの費用
- 研修費:仕事上必要な研修を受けた際の費用
- 資格取得費:仕事上必要な資格取得のために要した費用
- 帰宅旅費:単身赴任など、自宅と赴任先の往復に必要な交通費
原則的に、仕事において必要な経費が該当すると考えましょう。基準となる控除額は給与所得の金額によって変動します。基準に反映する年によって条件が異なる可能性があるため、申請する前にリサーチできると安心です。仕事関係の出費が負担に感じている方は、金額を計算して適用の可否を確かめましょう。
●メリット
- 所得税・住民税の控除を受けられる
●デメリット
- 確定申告が必要となる
- 対象となる経費が自己負担となるケースが限られている
- 勤務先の証明が必要
- 特定支出控除が適用される金額が高い
【特定支出控除がおすすめな人】
- 通勤手当が支給されていない人
- 転居を伴う転勤の際に、会社から転居費用が支給されていない人
- 仕事に関連するセミナーなどを自己負担で受講している人
- 仕事に関連する資格の取得のための勉強をしている人
- 単身赴任者で会社から帰宅旅費が支給されていない人
- 顧客との商談の際の飲食費を自己負担している人
ここに挙げたように、特定支出控除に該当する多額の費用を自己負担している人は、会社の証明を得られれば、確定申告で特定支出控除の適用を受けられるためおすすめです。
個人事業主におすすめ!節税対策のおすすめ4選

個人事業主として生計を立てている方は、青色申告を行ったり特例の控除制度を利用したりすることで節税効果が期待できます。現在会社に属していない方は、税金による経済的負担を軽減するためにも実践してみましょう。4つの対策方法をご紹介します。
青色申告を行う
1月1日~12月31日の間に行った取引の内容は、確定申告の書類に記入して税金を申告しなければなりません。大きく分けると青色申告・白色申告の2種類がありますが、節税効果を高めるのであれば青色申告がおすすめです。
期待できる効果
- 所得金額から最大65万円の特別控除が適用
- 生計を一にする配偶者や親族に青色事業専従者給与を支給できる
- 赤字が出た場合は翌年以後3年間の所得から差し引いて計上できる
●メリット
- 青色申告特別控除により、所得控除額が増える
- 妥当な金額であれば、配偶者や親族への給与に制限がなく、所得を分散できる
- 赤字が出た年がある場合、翌年以降の3年間で黒字の年があった場合に、所得税・住民税の負担が軽減される
●デメリット
- 白色申告よりも確定申告や記帳の手間がかかる
経費や控除の見直しをする
1年間に費やしている経費や控除の内容を明確にすることで、節税可能な部分を発見するきっかけになるかもしれません。仕事関係の移動や食事は経費の対象として計上できるため、以下のような項目に漏れがないかチェックしてみましょう。
- 事業を開始・拡大するためにかかった費用
- 取材や撮影のために購入した機材費
- 仕事上必要な移動のために費やした交通費
- 宣伝を行った際に支払った費用
- 取引先と食事をした際の接待費
自宅で行った業務が報酬として支払われている場合は、通信費や家賃なども経費に含まれます。ただし、プライベートと仕事の割合を算出する必要があります。1年間の作業時間を計算し、仕事に計上できる部分のみ経費として扱いましょう。
●メリット
- 少額の経費でも積み上げれば、節税効果が期待できる
●デメリット
- 経費に該当するものか、判断が難しいものがある
- 業種に見合った経費率を超えると、税務調査が入る可能性がある
減価償却の特例を利用する
仕事に利用する事務所や家電製品などの固定資産は、減価償却の特例(少額減価償却)を反映することで節税対策に活用できます。通常減価償却のルールを反映しますが、一定の条件を満たすことで適用される仕組みです。以下のいずれかに該当する場合に利用できます。
- 消耗性のものであり、合計300万円未満
- 購入金額が30万円未満のもの
計上の基準が商品単体でない点に注意しなければなりません。例えば、テーブルセットを購入した場合はテーブル・椅子の合計金額を基準にします。所得が高額な年度に特例を活用することで、課税額を減らして節約が可能です。固定資産を購入する機会が多い方は、金額を確認しながら制度を有効活用しましょう。
事業を法人化する
個人の事業が拡大して多額の収益を得ている場合は、法人化の手続きを行うのもひとつの方法です。法人税は法人の種類や所得金額によって区分されており、「所得が高額なほど税率が上がる」というものではありません。一般的な普通法人を例にあげると、2020年4月現在定められている税率は以下のとおりです。
- 年間800万円以下の部分:15%
- 年間800万円以上の部分:23.2%
上記の税率を適用したとき、個人の所得税よりも軽減できる場合は法人化を決断してもよいでしょう。具体的な目安は事業の規模や従業員数などによって異なるため、不安な方は税理士に相談できると安心です。
参考:『国税庁 法人税の税率』
●メリット
- 課税所得によっては、税金の負担を減らせる
- 役員報酬に給与所得控除が適用される
- 赤字を10年繰り越せる
●デメリット
- 法人の設立費用がかかる
- 1人会社でも社会保険への加入義務がある
- 赤字でも法人住民税の支払いが発生する
節税対策+資産運用を考えるなら不動産投資がおすすめ!
税金を節約するためには、自身の生活状況や収入などを把握したうえで選択しなければなりません。保険や投資など、お金を費やす方法はリスクもあるため入念なリサーチが重要です。
節税だけではなく資産運用も望んでいる方には、比較的リスクを抑えやすい不動産投資が向いているでしょう。
資産運用と節税の観点でのメリット
- ローンの活用で少ない資金からスタート可能
- 所得税や住民税の軽減
- 万が一の事態に備えた生命保険の機能
空室や自然災害のリスクをともないますが、長期的な運用を前提に始めると収益化につなげやすい方法です。魅力的な物件を選ぶには不動産会社選びも重要な要素となるため、信頼性の高い会社を探して節税の効果を実現しましょう。
マンション投資が節税になるカラクリとは?失敗しないためのポイントをわかりやすく解説
もぜひチェックしてみてください!
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
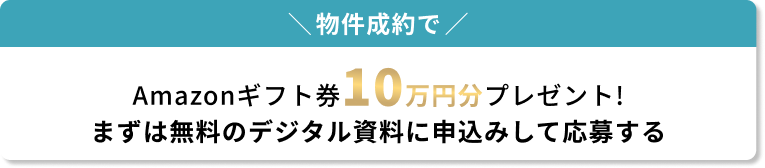
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ
普段何気なく過ごしている日々のなかにも多数の税金がかかわっています。個人年金や扶養といったポイントに注目すると、これまで支払っていた税金が節約できるかもしれません。実践しやすい方法を見つけ、少しでもお得な生活を送れるよう取り組んでみましょう。
資産の拡大にゴールを定めたい方は、節税効果が期待できる不動産投資がおすすめです。「投資経験がなく不安……」という場合はトーシンパートナーズへお任せください。初心者でも始めやすい体制を整え、希望に沿ったプランをご提案します。
<監修者プロフィール>
小菅 信也
株式会社トーシンパートナーズ 執行役員
1994年に株式会社トーシンパートナーズ新卒一期生として入社。投資用不動産の営業に従事。
2006年より営業企画課長、2015年に営業企画部長として、営業スタッフに関わる業務全般およびマーケティング施策の責任者として従事。
2021年にはマーケティング部門を立ち上げ、マーケティング部長も兼務。
2023年より上記全部門の担当役員となる。