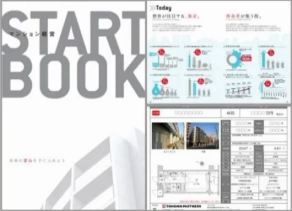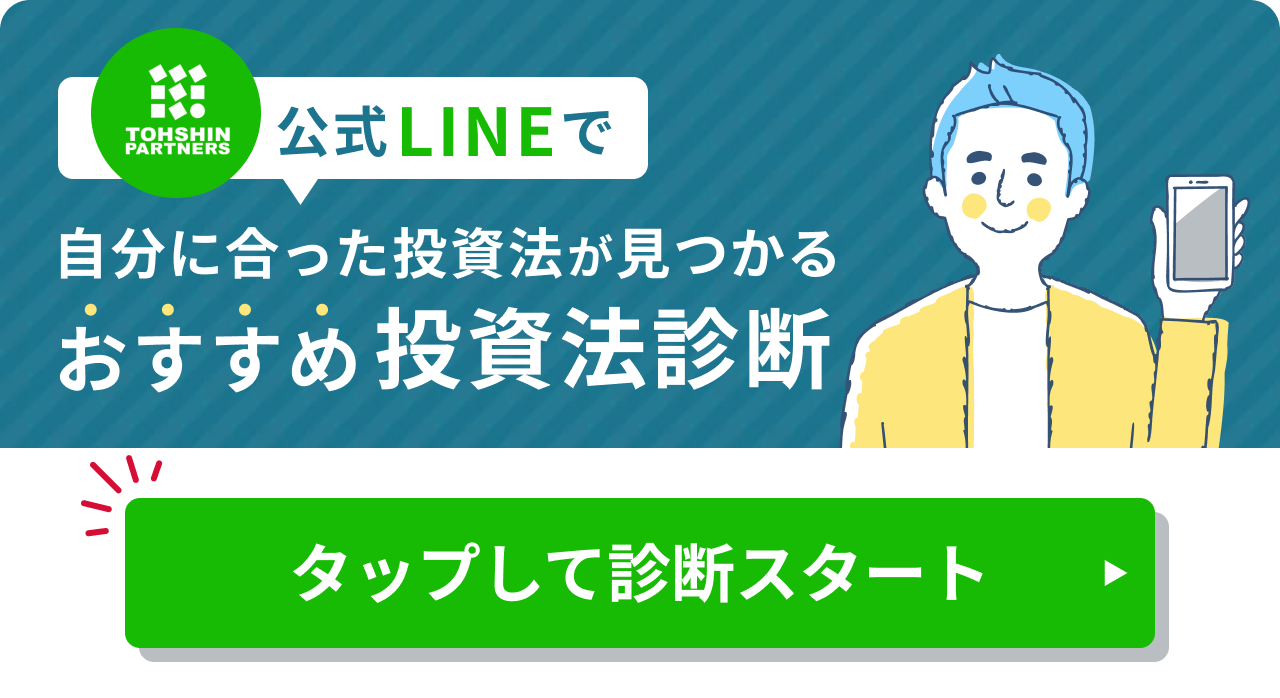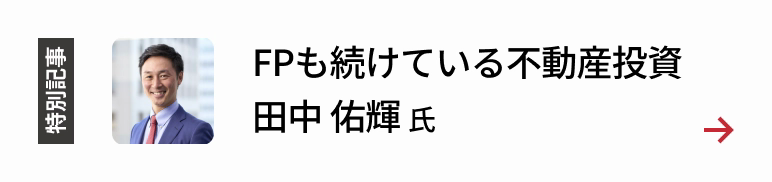不動産を所有したり、投資対象として運用したりすれば、節税になるということを聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、どのような仕組みで節税できるのかよく分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、不動産投資で節税できる税金の種類や、節税を考える上で注意したいポイントなどをご紹介します。将来的な資産形成のために不動産投資やマンション経営を検討している方は、役に立つ知識を得られるでしょう。
不動産投資を検討されている方へ
月々1万円の少額で始められる、不動産投資の全容がわかる資料を無料配布しています。
リスクを回避するためにも、弊社の実績と独自のノウハウを詰めた資料をぜひ参考にしてください。
不動産投資でできる3つの税金対策

不動産投資の大きな目的は、将来的な資産形成です。ローンを活用して物件を購入することで、大きな資金を使うことなく、ローン完済後に大きな価値を有する資産をつくることが可能です。
さらに不動産投資は、節税対策としても効果的です。所得税や住民税、贈与税、相続税の節税も期待できます。次項から、それぞれの節税のしくみを詳しく見ていきましょう。
1.所得税・住民税の節税

不動産投資をすると、誰にとっても身近な存在である所得税や住民税を節税できます。帳簿上で不動産所得が赤字になれば確定申告時に他の所得と損益通算され、トータルの課税額が低くなります。適切に経費計上することで本来払う必要のない税金を払ってしまうリスクを回避できますので、おおまかな仕組みを把握しておきましょう。
所得税・住民税とは
所得税とは、収入から費用を差し引いて算出される所得に課される税金のことです。一般的に会社員等の給与所得者の場合、所得税は給与から差し引かれています。住民税は、都道府県と市区町村から課される税金です。所得額に応じて税額が決定します。
日本の所得税は、所得金額が大きくなるほど税率も大きくなる「累進課税制度」を採用しています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表は、国税庁のウェブサイトに掲載されている所得税の速算表です。課税対象となる所得金額に税率を掛け合わせ、控除額を差し引けば、所得税を算出できます。
所得税・住民税が節税できるしくみ
所得税には、各種所得の合計額に課税される「総合課税」と、ほかの所得とは合算できず個別の納税が義務づけられている「分離課税」があります。総合課税の対象となる代表的な所得としては給与所得や事業所得がありますが、不動産所得も総合課税の対象です。
総合課税は、黒字所得から赤字所得を差し引く「損益通算」ができるメリットがあります。不動産投資で赤字が発生したとしても、給与所得などと損益通算することにより、赤字と黒字を相殺することが可能なため、結果として節税につながります。
不動産所得に計上可能な経費は?
不動産投資では、さまざまな費用を経費として計上できます。以下に挙げる経費をもれなく計上することで、所得税を抑えることが可能です。
- 租税公課:固定資産税・都市計画税・登録免許税など
- 損害保険料:火災保険・地震保険など
- 減価償却費
- 修繕費:設備の修理・壁の塗り替え・畳の張り替えなど
- 借入金の支払利息:不動産取得時に組んだローンの利息
- 管理費:建物管理会社や賃貸管理会社へ支払う費用
- 広告宣伝費:入居者募集などにかかる費用
- 交通費:打ち合わせ・物件の下見などの移動費
- 通信費:電話・インターネット代
- 新聞図書費:情報収集に使用した新聞や書籍の購入代
- 接待交際費:管理会社や税理士との打ち合わせで支払った飲食費など
- 消耗品費:デジカメ・プリンターなどの購入費
- 税理士報酬
このように、不動産投資において発生した費用の多くは経費計上できます。
2.贈与税の節税

不動産投資を続けていると、多くの方が生前贈与についても検討することになるでしょう。物件を現金に換えて贈与するより、不動産のまま贈与するほうが節税につながります。
ここでは、なぜ不動産のまま贈与すると節税につながるのかを理解しておきましょう。投資物件を残しておけば、家族の生活を守る手段にもなります。
贈与税とは
贈与税は、財産を他人から無償でもらった際、受け取った側に課される税金です。贈与された財産には、110万円の基礎控除が設定されているため、年間合計110万円までの財産なら贈与税はかかりません。贈与税は、以下の計算式で算出できます。
(受け取った財産額-110万円)×税率-控除額
税率と控除額は、基礎控除適用後の財産額により異なります。国税庁のウェブサイトに掲載されている、以下の「贈与税の速算表」を参考にしましょう。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
(参考:『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|相続税 |国税庁』)
贈与税が節税できるしくみ
不動産を贈与する際の贈与税の計算には、国税庁が定めた「相続税評価額」を使用します。不動産を贈与する際は時価ではなく、相続税評価額により贈与税を算出するのが基本的なルールです。
この方式により算出される不動産の評価額は、時価より2割~3割ほど下がります。これが不動産を現金に換えて贈与するより、そのまま不動産として贈与するほうが、節税につながる理由です。
なお、不動産取得直後に贈与した場合は、あからさまな節税対策として指摘される恐れがあるため注意しましょう。不動産の贈与には、登録免許税や不動産取得税が課され、贈与財産に対し5%ほどの税金がかかることも覚えておく必要があります。
3.相続税の節税

不動産の相続は、不動産の所有者が亡くなった時点で所有権が移転していない場合に発生します。不動産投資により相続税を節税できるしくみは、贈与税の場合と同じです。
ここでは、相続税の大まかな計算方法と、節税の考え方を理解しておきましょう。相続対策として不動産投資を行えば、税金面で有利に働くことが分かります。
相続税とは
相続税は、故人から財産を相続する際、相続人に課せられる税金です。相続税は、以下のステップで算出します。なお、配偶者の税額軽減制度により、一定の条件を満たした配偶者は税額が優遇されます。
- 遺産総額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出する。基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算する。
- 課税遺産総額から法定相続分をもとに算出した各相続人の取得金額に所定の税率をかけ、控除額を差し引く。算出した各人の相続税額を合計する。
- 相続税額の総額を各相続人の課税価格に応じて割り振り、それぞれに課される税額を算出する。
相続税の具体的な計算方法について詳細を知りたい人は以下の参考サイトに記載されているので、ぜひ確認してみてください。
参考:『相続税の計算|国税庁』)
相続税が節税できるしくみ
不動産投資による相続税の節税は、贈与税の場合と同じです。贈与税は、相続税評価額により算出されるルールでしたが、相続税も同様に相続税評価額により計算します。
たとえば、現金1億円相続した場合と、現金を1億円の不動産に換えて相続した場合を考えてみましょう。現金で相続するケースでは、1億円がそのまま課税対象となりますが、不動産として相続する場合は、評価額が8,000万円程度まで下がります。
課税対象額が引き下げられれば相続税も下がるため、節税が可能です。借地や借家を相続する場合は、さらに相続税評価額が下がる可能性があることも覚えておきましょう。
税金対策における法人化のメリット・デメリット
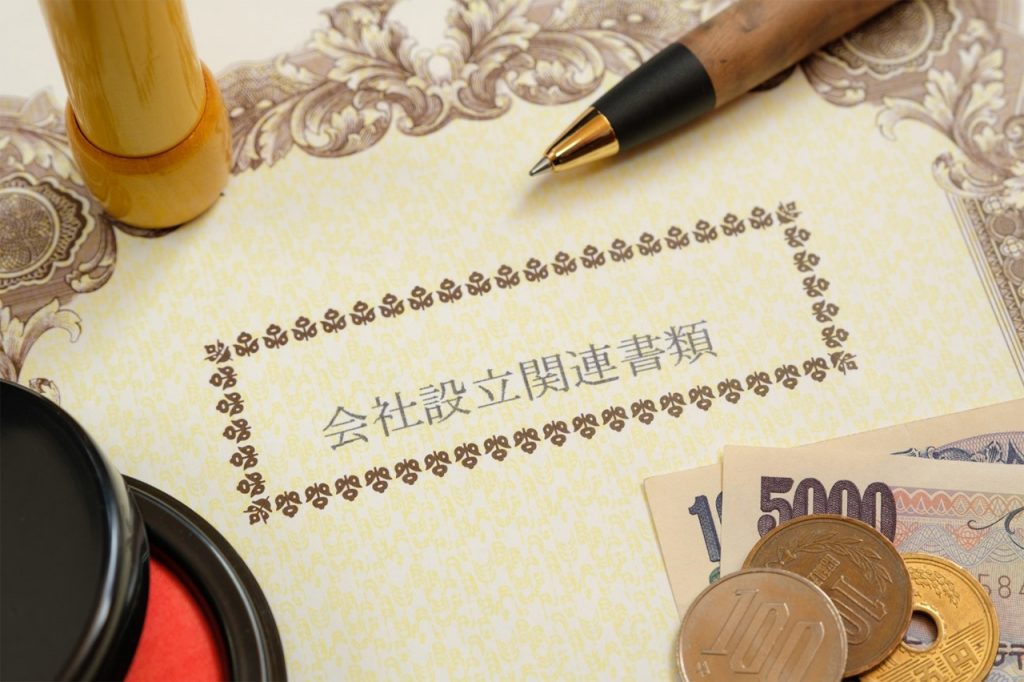
節税したい場合に、法人化すればよいという意見を聞いたこともあるでしょう。確かに法人化にはメリットがありますが、同時にデメリットも発生します。
ここでは、不動産投資を事業の中心に考えた場合の、法人化におけるメリット・デメリットを理解しておきましょう。安易に法人化すると、逆にデメリットが大きくなることに注意が必要です。
法人化のメリット
個人にかかる所得税と住民税は、累進課税制度により所得に応じて税金が定められ、最大税率は55%です。一方、法人にかかる法人税は最大税率が33%であるため、所得が多い場合は法人化するほうが有利です。
また、法人で不動産を所有している場合は、家族を役員にして家賃収入を役員報酬とすることで、計画的に財産を移転できます。結果として、贈与税や相続税の節税につながるでしょう。
法人化のデメリット
法人を設立する場合、さまざまな費用が発生します。株式会社を立ち上げるケースでは、少なくとも20万円程度の諸経費が発生するため注意が必要です。司法書士への依頼費や印鑑購入代などもかかります。
また、社会保険への強制加入も頭に入れておかなければなりません。法人を立ち上げると、社会保険への加入が必須となります。個人で負担していた国民年金や国民健康保険に比べ、社会保険料は負担額が大きくなることも覚えておきましょう。
さらに法人では、どのくらい利益を上げているかに関係なく、事業規模に応じて毎年一定の法人住民税がかかります。一般的に、個人で支払っていた住民税より税額が高くなるため注意しましょう。
不動産投資で法人化する方法を詳しく知りたい方は「不動産投資で法人化をするには?メリットやデメリットも解説」をチェック
不動産投資で税金対策を行う上での心がまえ

不動産投資に取り組む場合、節税対策だけを目的に運用を進めていくことはおすすめできません。本来の投資目的を見失わずに、収益を上げていくことが重要です。
また、物件購入時にローンを組めなければ物件を現金購入する必要があり、用意できなければ不動産投資を始めることは不可能です。不動産投資を始めるにあたり心がけておきたいことを、以下にいくつかご紹介します。
節税だけにとらわれない
不動産投資の目的は、あくまでも将来の収益獲得や資産形成にあります。節税を主目的とした不動産投資は、本末転倒といわざるをえません。しっかりと資産を構築できるような運用を心がけることが重要です。
前述したように、贈与や相続を見越した不動産の購入は、取得した時期によっては税務署から指摘を受ける恐れもあります。節税できる仕組みを理解しつつ、資産形成を重点に置いた運営を目指し、「節税もできる」程度の意識にとどめておきましょう。
さまざまな節税方法を視野に入れる
節税の方法は、不動産投資だけではありません。たとえば、個人年金保険に加入すれば、個人年金保険料控除を受けられるため節税効果が期待できます。
個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の活用もおすすめです。iDeCoは控除の上限がなく、税制面で優遇されています。このように、資産形成しながら節税できる方法にはさまざまな選択肢があるため、自分に合った方法を選べるよう常にアンテナを張っておくようにしましょう。
初心者は区分ワンルーム・コンパクトマンション投資から始めよう
不動産投資は節税に有利だということが理解できても、投資初心者は何から始めればよいのか分からないことも多いのではないでしょうか。初めて不動産投資に取り組む場合は、区分所有のワンルーム・コンパクトマンション投資から始めるのがおすすめです。
丸ごと物件を購入する1棟投資とは異なり、区分マンションなら1室から購入できるため、少ない自己資金から始められます。
新築物件は中古物件と比較すると担保価値が高く金融機関からの融資が受けやすくなるので特に初心者の方へおすすめの投資方法です。不動産投資を検討している場合は、最優先で取り組んでみましょう。
マンション投資を詳しく知りたい方は「ワンルームマンション投資のメリットやリスクとは?」をチェック
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
まとめ

不動産投資では、3つの税金対策ができます。それぞれにメリットがあるものの、節税だけにとらわれず、あくまでも本来の目的である資産形成に注力することが重要です。リスクと初期投資を抑えながら不動産投資に挑戦したい初心者の方には、区分所有のワンルーム・コンパクトマンション投資をおすすめします。
不動産投資や節税対策に興味がある方は、ぜひトーシンパートナーズにご相談ください。首都圏の人気エリアの物件をご紹介し、お客様の考え方に合ったプランをご提案します。