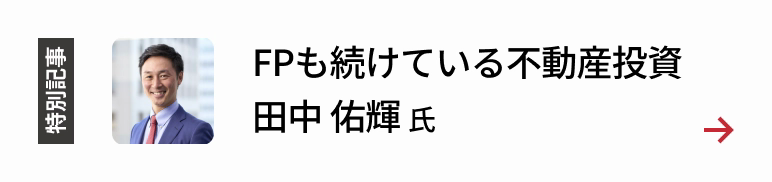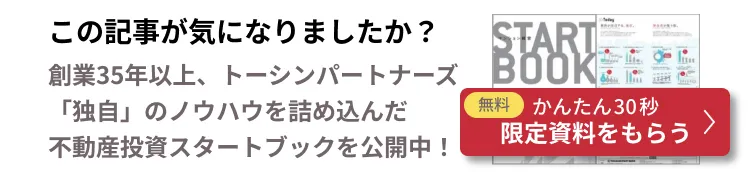- 不動産投資の基礎知識
マンション経営に資金計画が大切な4つの理由!8つの初期費用と資金を抑えるポイントを解説

マンション経営による資産形成・資産運用を検討していて、どの程度資金が必要なのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
マンション経営では物件の購入と管理の双方にさまざまな費用が発生するため、長期的な視点で資金計画を立てることが重要です。購入費用や諸費用の内訳を知るだけでなく、ローンの組み方や資金を抑える工夫を理解しておくことで、少ない自己資金でも効率よく資産形成を目指すことが可能です。
マンション経営を始めるのなら、どのような費用がかかるのか、資金はどれほど必要なのかを把握しておきましょう。この記事では、マンション経営に必要な資金の内訳や資金計画の立て方、費用を抑える工夫、よくある失敗とその対策まで詳しく解説します。
マンション経営において資金計画が重要な4つの理由

マンション経営を始める際には、物件の選定やローンの組み方など、さまざまな準備が必要になります。中でも特に重要なのが「資金計画」です。自己資金や借入額の配分、長期的な収支の見通しをあらかじめ立てておくことで、経営上のリスクを抑え着実な資産形成につなげることができます。
ここでは、マンション経営において資金計画がなぜ重要なのか、4つの理由を解説します。
初期費用だけでなく運用コストも想定するため
マンション経営では、物件の購入費用や登記費用といった初期費用だけでなく、運用中にかかるさまざまなコストを見込んでおく必要があります。
例えば、毎月の管理費や修繕積立金、年単位で発生する固定資産税・都市計画税などは、継続的な支出です。さらに、空室が出た際の入居者募集費用や、給湯器やエアコンの故障といった突発的な修繕費も想定しておかなくてはなりません。
このような支出を軽視したまま経営をスタートすると、想定していた収支計画がすぐに崩れ、思わぬ赤字経営に陥るリスクがあります。短期的な利益にばかり目を向けるのではなく、長期的な運用コストをしっかりと資金計画に織り込むことが重要です。
借入額・返済計画・自己資金のバランスを見極めるため
借入額・返済計画・自己資金のバランスを見極めるためには、投資家自身の資金状況とリスク許容度を踏まえた綿密な計画が欠かせません。ローンを多く借りれば、少ない自己資金でマンション経営をスタートできるメリットがある反面、返済額が増え空室時や収入の変動時に資金繰りが厳しくなる可能性もあります。一方、自己資金を多く投入すれば毎月の返済負担は軽くなりますが、手元資金が減ることで、突発的な修繕費や空室対策費に柔軟に対応できなくなるリスクもあります。
大切なのは「どれくらいの借入額なら無理なく返済できるか」「どの程度の自己資金を残しておくと安心か」というバランスを冷静に見極めることです。資金計画を通じて、自分にとって最も現実的かつ持続可能な返済モデルを構築することが、安定したマンション経営につながるでしょう。
長期的な収支シミュレーションでリスクを可視化するため
マンション経営は、短期的な収益を求める投資ではなく、長期的な視点で行う資産運用です。したがって、10年、20年先を見据えた収支のシミュレーションが重要です。
- 家賃収入が将来的にどう推移するか
- 金利が上昇した場合に返済額はどうなるか
- 築年数が経過することで修繕費はどの程度かかるのか
上記を想定した複数のシナリオで試算を行うことで、リスクを把握できます。また「何年で投資額を回収できるか」「繰り上げ返済によってどれだけ利息を軽減できるか」といった、具体的な計画を立てることも可能になります。こうした見通しを持つことで、マンション経営への心理的な不安も軽減され、より冷静で戦略的な判断ができるでしょう。
レバレッジ効果を活かし資産形成を加速するため
不動産投資の大きな魅力の1つが「レバレッジ効果」を活用できることです。ローンを利用することで、自己資金が少なくても大きな資産を手に入れることができ、将来的には家賃収入や売却益などにより、投資元本以上のリターンが得られる可能性があります。
しかし、このレバレッジ効果を安全かつ効果的に活かすためには、綿密な資金計画が欠かせません。物件価格に対する借入比率(Loan to Value)や返済期間、金利タイプの選定など、収支の安定性に直結する項目はすべて資金計画に含まれます。
さらに、収支が安定していれば、将来的に複数物件への投資を検討することも可能です。こうした「攻め」の戦略を取るためにも、初期の段階からしっかりとした資金計画を立てておくことが、長期的な資産形成を加速させるうえで重要となります。
マンション経営に必要な資金計画の立て方

資産価値の高い物件を将来の大きな資産として手に入れるためには、ローンを活用して、長期的な資金計画を立てることが重要です。マンション経営にとって必須といえる資金計画の立て方を見ていきましょう。
物件の購入や管理に必要な金額を計算する
マンション経営では物件の購入や管理にさまざまな費用がかかるため、必要な金額やキャッシュフローを計算し、無理なく資産運用ができるかシミュレーションすることが重要です。物件の購入時にかかる費用をまとめると、以下の8種類があります。
- 物件の購入費用(頭金とローン)
- 不動産の仲介手数料(仲介で購入する場合のみ)
- 印紙代
- 登記費用
- ローン手数料
- 火災保険料
- 不動産取得税
- 司法書士報酬
物件の購入費用はローンでカバーできても90%までと考えておきましょう。ローンと頭金以外の諸費用は物件価格の8%~10%程度を目安とすると、物件価格の20%程度の自己資金を用意しておくと安心です。実際には、さらに初期費用を抑えられる可能性があり、10万円程度で始められることもあります。
物件の運用中には固定資産税や都市計画税、修繕費用やリフォーム費用、管理費用もかかります。ローンの返済を無理なく続けていけるように、長期的な資金計画を立てることが重要です。
借入額と自己資金のバランスを考える
ローンの返済負担軽減を考えると、自己資金の準備期間を長く取り、頭金を多く支払うことを考えるかもしれません。しかし、ローンを利用するメリットのひとつは小さい資金で投資を行え、収益性を高めていけるという「レバレッジ効果」です。少ない自己資金で大きな資産を形成するという視点も持ちましょう。
頭金の比率を大きくするほど毎月の返済額は少なくなり、収益性は高くなるように見えます。しかし、自己資金を投入すればするほど、レバレッジ効果の恩恵を受けにくくなります。自己資金を投入しすぎると手元のキャッシュが少なくなるため、マンション経営で発生する費用負担への蓄えが少なくなるというデメリットもあります。
借入額を抑えて返済負担を小さくすることと、自己資金を投入しすぎないことの両立を考え、バランスよくローンを活用しましょう。
借入期間を考える
借入額と自己資金のバランスは短期的な視点でも考えられますが、長期的な視点から借入期間を考えることも重要です。ローンを提供する金融機関は多く、借入期間の設定は一律ではありません。
金融機関によっては、15年程度の比較的短期のローンから、30年や35年という長期ローンを提供しているケースもあります。短期ローンを選択すると、早い段階で完済できるメリットがありますが、月々の返済負担が大きいことはデメリットです。
長期ローンでは月々の返済負担は抑えられますが、短期ローンより元金の減りが遅く、総返済額は大きくなります。両者のメリットを生かしてリスク分散できるのが、短期と長期を組み合わせたタイプのローンです。自身のライフプランを考えて、適切なタイミングで完済できる借入期間を選択しましょう。
固定金利か変動金利かを決める
ローンは金利が変動するかどうかで「固定金利」と「変動金利」の2種類に大別できます。
固定金利は変動金利より金利が高く設定されていますが、少なくとも一定期間は金利の変動がなく、返済計画が立てやすい点はメリットです。「全期間固定金利型」と「固定金利選択型」に分かれ、全期間固定金利型は全期間を固定金利で返済するため、金利変動リスクがありません。
変動金利の特徴は半年に1回金利の見直しが行われることです。金利が低いときには負担が減りますが、金利が高くなると負担も大きくなるリスクがあります。
固定金利選択型は先に設定した期間は固定金利ですが、期間が終了した時点の金利で固定金利か変動金利を再選択します。元金の減りの早さや金利変動リスクを踏まえ、計画的に固定金利か変動金利を選択しましょう。
繰り上げ返済を視野に入れる
商品によっては、残債の一部または全部の「繰り上げ返済」に対応しています。繰り上げ返済では元金のみを返済できるため、残債を一気に少なくして、その後の利息を減らせることがメリットです。
繰り上げ返済で減った残債の処理については、「返済額軽減型」と「期間短縮型」の2種類があります。返済額軽減型は借入期間を据え置きにして、月々の返済額を少なくできる方法です。期間短縮型は月々の返済額を据え置きにして、返済した分の借入期間を短縮します。
繰り上げ返済に対応している金融機関でも、手数料を設定している場合もあることには注意しましょう。繰り上げ返済を選択できる余裕があるかどうかも視野に入れ、長期的なシミュレーションによって資金計画を立てることが重要です。
不動産投資のリスクとメリットがゼロからわかる、スタートブックの無料プレゼントはこちら
マンション経営を始めるのに必要な8つの資金の内訳と金額目安

マンション経営を始めるにあたっては、まず初期費用がどれほどかかるかを把握する必要があります。物件の購入費用は大部分をローンでカバーできますが、諸費用に関しても軽視できる金額ではありません。物件の購入費用や諸費用の内訳と金額の目安を見ていきましょう。
物件の購入費用
マンション経営を始めるに当たっては、ワンルームなどの区分所有マンションや1棟マンションといった収益用不動産を購入することになります。物件価格は規模、築年数や立地などの条件によってさまざまです。
土地を持っている場合にはマンションやアパートの建築もできます。建築費は木造、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)によって相場が変わります。
物件の購入費用や建築費用の大部分は「アパートマンションローン(不動産投資ローン)」でカバーできます。自己資金が必要になるのは頭金とその他の初期費用の部分です。
不動産の仲介手数料
収益用不動産の購入を不動産会社が仲介した場合、不動産会社に対して「仲介手数料」を支払います。仲介手数料には上限が定められており、売却価格によって以下のように異なります。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |
| 400万円超 | 売却価格の3% +6万円 +消費税 |
| 200万円超400万円以下 | 売却価格の4% +2万円 +消費税 |
| 200万円以下 | 売却価格の5% +消費税 |
その額は200万円以下の部分に5%、200万円を超え400万円以下の部分に4%、400万円を超える部分に対して3%(いずれも税抜き表示)です。
計算を簡単にするために、400万円以上の物件には「物件価格×3%+6万円+消費税」で上限額を求めます。2,000万円の物件なら72万6,000円、4,000万円の物件なら138万6,000円が上限です。実際の請求額は上限額を下回るケースもあります。
印紙代
物件の売主とは「不動産売買契約書」、アパートローンを契約した金融機関とは「金銭消費貸借契約書」を締結し、契約の内容や金額を証明します。
これらの課税文書には、記載された金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要です。収入印紙代は以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
不動産売買契約書の場合は、物件価格が500万円を超えて1,000万円以下なら5,000円、1,000万円を超えて5,000万円以下なら1万円、5,000万円を超えて1億円以下なら3万円の収入印紙を貼り付けます。貼り付けた収入印紙に適切な消印をしなかった場合、過怠税を徴収されることに注意しましょう。なお、この金額は令和9年3月31日までの適用です。※令和7年7月現在
参照元:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
登記費用:登録免許税
マンションを購入したり建築したりする場合には、物件の権利関係を証明するための「登記」を行い、「登録免許税」の支払いが必要です。
物件をローンで購入する場合には、物件の所有権を証明する「所有権移転登記」と、物件を担保に抵当権を設定したことを証明する「抵当権設定登記」を行います。物件を建築する場合には「所有権保存登記」や「建物表題登記」が必要です。
新築建物の所有権保存登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、抵当権設定登記では借入額の0.4%がかかります。
ローン手数料
マンションは購入するにしても建築するにしても高額であるため、多くの投資家はローンを利用してマンション経営を始めます。ローンを契約する際には、金融機関に対して手数料の支払いが必要です。
手数料の内訳や費用は金融機関によって設定が異なり、物件の資産価値によっても金額は上下します。手数料は定額の場合もありますが、借入額に対して1%~3%程度になることが一般的です。
火災保険料
ローンの契約にあたっては、担保である物件を守るために、火災保険の加入が融資条件に含まれる場合もあります。火災保険は火災・落雷・強風による被害を補償しますが、津波・火山噴火の被害までカバーするには地震保険の加入も必要です。
天災による被害への備えは重要であるため、義務付けられていなくても加入は必須といえるでしょう。火災保険料は保険会社やプラン、物件の構造や広さによって異なります。ワンルームマンションの場合は5年契約で3〜5万円程度が相場です。
不動産取得税
マンションを購入や建築により取得した場合、取得した本人は「不動産取得税」の支払いが必要です。税額は「固定資産税評価額×4%」が原則ですが、2027年3月31日までに取得した物件に限り、軽減措置により「固定資産税評価額×3%」の計算に
引き下げられます。
不動産取得税の注意点は、請求のタイミングが物件の取得時ではなく、半年から1年半後になることです。物件によっては納税額が100万円以上になる場合もあるため、支払いを加味した資金計画を立てましょう。
登記費用:司法書士報酬
マンション経営のスタートにあたっては、専門知識が必要な各種登記を行うため、司法書士に登記業務を依頼することが一般的です。司法書士は売買契約の立ち会いも行います。
司法書士事務所によって費用の設定は異なりますが、総額で10万円前後になることが一般的です。専門知識は必要ですが手続きの内容は一律であるため、報酬が安い近隣の司法書士事務所に依頼しましょう。
資金を抑えてマンション経営を始める4つの工夫

マンション経営を始めたいと考えていても「初期費用が高そう」「自己資金が少ないから不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、物件選びやローンの活用方法を工夫することで、想像以上に少ない資金からでもマンション経営を始めることが可能です。
ここでは、初期投資を抑えながらも安定した経営を目指すための4つの具体的な方法を紹介します。
区分ワンルームマンションを選ぶことで初期費用を抑えられる
マンション経営を始めるにあたって最もコストを左右するのが「物件価格」です。そのため、なるべく初期費用を抑えるには、物件の種類に着目することがポイントです。
区分所有のワンルームマンションは、1棟まるごと所有するアパートやマンションに比べて、物件価格が大幅に低く設定されています。結果として、必要な頭金やローンの借入額も抑えることができ、自己資金が限られている人でも参入しやすい特徴があります。
さらに、ワンルームタイプのマンションは、都市部の単身世帯から安定した需要が見込めるため、空室リスクも比較的低めです。特に駅から徒歩圏内にあるなど立地条件の良い物件であれば、入居者が見つかりやすく、長期的に安定した収益が期待できます。
諸費用ローンを利用して手元の資金を残しておく
物件価格に目が行きがちですが、実際にマンションを購入する際には、登記費用や仲介手数料、火災保険料など、さまざまな「諸費用」が発生します。これらの費用は一般的に物件価格の7~10%程度にのぼることもあり、思いのほか大きな負担になるケースがあります。
こうした諸費用に対しては「諸費用ローン」を活用することで、初期の自己負担を軽減することができます。諸費用ローンは、物件価格とは別に契約される融資であり、手元資金をなるべく減らさずに不動産投資をスタートできるのがメリットです。
もちろん、諸費用もローンに組み込む分の利息や返済期間には注意が必要です。しかし、想定外の修繕や空室発生時に備えるための「余剰資金」を手元に確保しておけるという意味では、資金繰りの安定性を高める有効な手段といえるでしょう。
築浅・リノベ済みなど状態の良い物件を選ぶ
初期投資額を抑えたいとき、安さだけで築年数の古い物件を選んでしまうのは要注意です。安く購入できても、設備の劣化や建物の老朽化により、早期に大規模な修繕や入居者対応が必要になるケースもあるため、結果的にコストが膨らむ可能性があります。
そのため、購入時には「築浅物件」や「リノベーション済み物件」など、状態の良い物件を選ぶのが賢明です。リノベ済みであれば、すでに内装が整っており、すぐに賃貸に出すことが可能な場合も多く、初期のリフォーム費用をカットできます。
また、築年数が古い物件であっても、管理状態が良好な物件は、資産価値の維持が期待でき、長期的な運用にも向いています。物件価格だけでなく、共用部分の清掃状況や管理組合の修繕計画などにも目を向け、管理の質が高いかどうかを見極めることが大切です。
総じて、マンション経営では「安い物件」ではなく「管理の行き届いた状態の良い物件」を選ぶことが、長い目で見たコストパフォーマンスの向上につながります。
交渉により支払金額を減らす
マンション経営にかかる初期費用は、必ずしも提示額どおりでなければならないわけではありません。実は、交渉によって支払金額を抑えられるケースもあります。例えば、仲介手数料は上限が定められているものの、業者によってはキャンペーンなどで割引に応じてもらえることがあります。また、不動産会社と信頼関係が構築できていれば、柔軟な対応をしてもらえる可能性もあるでしょう。
さらに、長期間売れ残っている物件や、売主が早期売却を希望している物件であれば、価格交渉がしやすくなります。購入前に周辺の相場を調べ、根拠をもって交渉することで、物件価格そのものを下げられることもあります。こうした交渉によるコスト削減も、資金を抑えたマンション経営には有効な戦略です。
マンション経営の管理・運営に必要な資金の内訳と金額目安

マンション経営では購入時だけでなく運用中にもさまざまな費用が発生します。固定資産税・都市計画税は毎年の支払いが必要で、入居者募集や修繕・リフォームにかかる費用の支払いも必要です。さらに、建物管理や入居者管理を管理会社に委託する場合、家賃の数%にあたる管理費用が発生します。
固定資産税・都市計画税
固定資産税は1月1日時点の固定資産の所有者に課税される地方税です。マンションや土地などのオーナーは毎年支払う必要があります。税額は「固定資産税評価額×1.4%」です。
市街化区域内にあるマンションを所有しているなら、「都市計画税」の支払いも必要です。税額は「固定資産税評価額×税率0.3%(税率は自治体によって異なる)」で計算し、固定資産税とともに徴収されます。
入居者募集の費用
マンション経営はどんなに人気のマンションでも空室が発生する場合もあります。空室の発生時には入居者募集が必要です。
入居者募集に際しては、インターネット上などでの宣伝費用と不動産会社への仲介手数料がかかります。費用の総額は家賃の3か月分程度が目安です。入居者の決定までは一時的に家賃収入が発生しないため、空室リスクに備えて余裕のある資金計画を立てましょう。
修繕・リフォーム費用
マンションは運用中に経年劣化が進み、入居者の退去時には原状回復も必要であるため、修繕費用やリフォーム費用を計算に入れることも重要です。建物や設備の破損を直すための費用を修繕費用、原状回復の場合はリフォーム費用と呼びます。
金額は施工の内容によってさまざまです。数百万円単位の大規模な修繕であれば、物件のオーナーが毎月積み立てる「修繕積立金」を利用できます。リフォーム費用に関しては、入居者から預かる「敷金」による相殺が可能です。
管理費用
マンション経営では共用部分の清掃や入居者からの家賃徴収など、さまざまな管理業務が発生します。会社員など本業がある方は、「建物管理」や「入居者管理」は管理会社に委託するのが一般的です。
会社員が副業でマンション経営を行うなら、信頼できる管理会社との連携は不可欠といえるでしょう。管理費用の金額は管理会社によって異なりますが、家賃の5%程度の設定が一般的です。
30年分の不動産投資ノウハウを詰め込んだ、スタートブックの無料プレゼントはこちら
マンション経営の資金計画でよくある5つの失敗とその対策

マンション経営は長期にわたって安定収入を見込める資産運用の手段ですが、しっかりとした資金計画がなければ、収支が悪化し、思わぬ損失を招く可能性もあります。特に初心者に多いのが「想定外の支出」や「甘い収支見積もり」によって資金繰りが苦しくなるケースです。
ここでは、マンション経営においてよくある資金計画上の5つの失敗パターンと、それぞれの対策を紹介します。事前に対策を知っておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
ローン返済額を過小評価して資金繰りが苦しくなる
マンション経営を始める際、多くの人が「家賃収入でローンを返済すればいい」と考えがちです。確かに、家賃収入が継続していればローン返済も可能ですが、実際には空室や家賃の下落といった不確定要素があります。
特に、ボーナス払いを前提にしたり、短期ローンで毎月の返済額が高くなったりするような計画を立ててしまうと、収入が少し減っただけでも資金繰りが一気に苦しくなる可能性があります。万が一に備えて、日常の生活費とは別に数ヶ月分の余剰資金を確保しておくことで、空室や突発的な出費にも柔軟に対応できます。加えて、返済遅延が続けば信用情報に傷がつき、将来の融資にも影響を及ぼします。
修繕費や税金など将来の支出を見落とす
マンション経営では、購入時の諸費用だけでなく、継続的に発生する運用コストの見落としにも注意が必要です。例えば、固定資産税や都市計画税、修繕積立金、管理費などが毎年かかります。築年数が経つごとに修繕の頻度や範囲が広がり、将来的に大きな出費が必要になるケースも珍しくありません。
こうした支出は事前に収支計画に組み込む必要があります。物件を選ぶ際には、修繕履歴や今後の修繕スケジュール、管理費の妥当性なども確認し、突発的な支出を想定したシミュレーションを行うことが大切です。日頃から一定額の資金を確保しておけば、不測の事態にも備えやすくなります。税制の改正によって課税額が変動する可能性もあるため、最新の情報を確認しましょう。
金利や借入条件のリスクを軽視してローンを組む
金利の種類や借入条件の違いは、マンション経営のキャッシュフローに大きく影響します。例えば変動金利を選ぶと、金利が上昇した際に返済額が膨らむリスクがあります。また、融資にかかる手数料や保証料、団体信用生命保険(団信)などの付帯費用を見落とすと、想定以上に実質的な支出がかさんでしまう点にも注意が必要です。
金利タイプは慎重に検討すべき項目です。将来の金利変動に不安があるなら、全期間固定金利型や一定期間だけ固定される固定期間選択型なども視野に入れるとよいでしょう。加えて、複数の金融機関で事前審査を受けて条件を比較すれば、より現実的で安心できる資金計画が立てられます。将来的に複数物件を保有したい場合は、今の借入条件が将来の融資枠にも影響します。
初期費用を自己資金だけでまかなおうとする
「借金をなるべくしたくない」と考えて、初期費用をすべて自己資金でまかなおうとする方は少なくありません。しかし、頭金や仲介手数料、登記費用、火災保険料などをすべて自己負担で支払ってしまうと、手元資金が一気に減少し、運用開始後の突発的な支出に対応できなくなるリスクがあります。
特にマンション経営では、空室発生時の広告費や設備の故障といった予期せぬ支出がつきものです。そうした事態に備えて、一定の余剰資金は常に確保しておく必要があります。
初期費用の一部については、諸費用ローンを活用することで自己負担を抑えることが可能です。ローンを上手に取り入れて手元資金を温存しておけば、経営の柔軟性と安定性が高まり、長期的にもリスクに強い資金計画を実現できます。
収支シミュレーションが楽観的すぎる
資金計画の段階で「家賃が一定期間ずっと維持される」「空室は発生しない」といった前提で収支シミュレーションを組んでしまうのは非常に危険です。実際の運用では以下のリスクに備えておく必要があります。
- 空室の発生
- 家賃下落
- 設備の劣化
- 突発的な修繕
- 家賃滞納など
理想的な収支だけでなく、最悪のシナリオも含めて複数のケースで試算を行うことが重要です。例えば「空室が3ヶ月続いた場合」や「家賃が10%下落した場合」といった、実際に起こり得る状況を想定したシミュレーションを行うことで、いざというときの備えができ、長期的な経営の安定にもつながるでしょう。出口戦略まで見据えたうえで、慎重かつ柔軟な資金設計を心がけることが重要です。
マンション経営の資金調達のポイント

マンション経営では物件の購入にも管理にも費用が発生するため、自己資金に不安を感じるかもしれません。マンション経営で必須といえるローンについて見ていきましょう。自己資金ゼロでマンション経営が始められるかどうかも解説します。
マンション経営の資金調達の方法は?
マンション経営を始めるにあたっては、物件の購入費用だけで数千万円の自己資金が必要に見えるかもしれません。実際には、投資家の多くはローンを活用して資金調達を行い、少ない自己資金でマンション経営を始めます。
融資の上限額は物件の収益性や資産価値によって異なり、金融機関によっても一律ではありません。
自己資金ゼロでもマンション経営はできるのか?
物件の購入費用を全額カバーできるローンを「フルローン」と呼びます。中古アパートやワンルームマンションではフルローンで審査に通ることもあるでしょう。しかし、審査基準は厳しいと考えてください。
さらに諸費用までカバーする諸費用ローンは金利が高く、月々の返済額が大きくなってしまうため、利用する場合はプロの意見を聞きつつ自身にあったプランを選びましょう。
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
Amazonギフト券10万円分
プレゼントキャンペーン
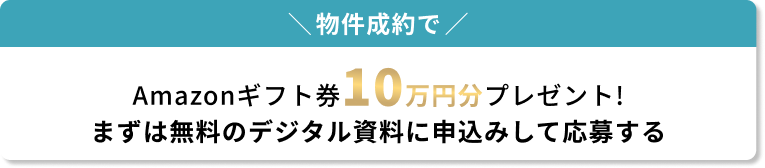
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
-
以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
-
専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
-
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
-
本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ
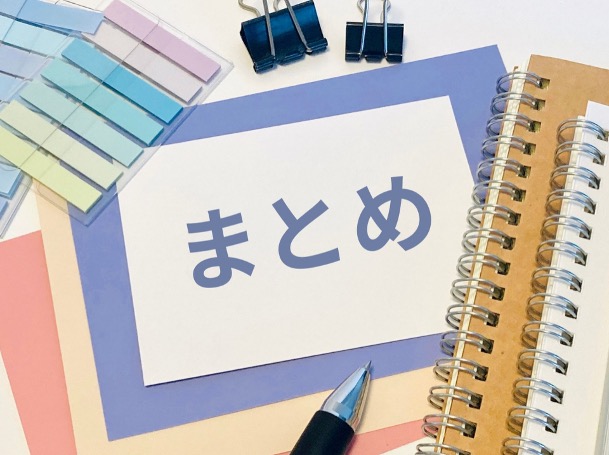
マンション経営では物件の購入と管理の双方にさまざまな費用が発生するため、自己資金と借入金のバランスを考え、長期的な視点で資産運用のシミュレーションをすることが重要です。少ない自己資金で大きな資産を手に入れる、ワンルームマンション経営をぜひご検討ください。
トーシンパートナーズでは将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」を展開しています。マンション経営や資金計画についてお悩みの方はトーシンパートナーズにご相談ください。
マンション経営の資金計画に関するよくある質問
Q1. 自己資金が少なくてもマンション経営は始められますか?
自己資金が少なくても、フルローンや諸費用ローンを活用することでマンション経営を始めることは可能です。特に、収益性が高い物件や築浅のワンルームマンションなどは、金融機関の融資審査に通りやすい傾向があります。ただし、ローンによる借入額が大きくなると、返済額が増えてキャッシュフローに余裕がなくなり、空室や修繕といった突発的な支出に対応できなくなるリスクもあります。
また、初期費用をすべて自己資金でまかなうのではなく、あえてローンで諸費用を賄い、一定の余剰資金を手元に残しておくという選択肢もあります。確かに借入額は増えますが、急な支出や空室リスクへの備えがあることで、長期的には安定した経営につながるでしょう。
また、金融機関や物件によっては、一定の自己資金を求められるケースもあるため、事前に必要な資金の目安を把握し、シミュレーションしておくことが大切です。
Q2. 資金計画を立てる際のシミュレーション期間はどれくらいが目安ですか?
資金計画を立てる際のシミュレーション期間は、基本的にはローンの返済期間に合わせて20〜35年程度の長期を見据えるのが望ましいです。マンション経営は短期的な収益だけでなく、長期的な資産形成を目的とするものなので、家賃下落や修繕費の増加、金利変動など、将来に起こり得る変化も加味して、複数パターンの収支を試算しておくと安心です。
また、出口戦略や繰り上げ返済のタイミングも視野に入れた計画を立てることで、より現実的で柔軟な資金運用が可能となります。シミュレーションは一度で終わらせるのではなく、定期的に見直すことも忘れないようにしましょう。
Q3. 固定金利と変動金利で資金計画に向いているのはどちらですか?
固定金利と変動金利にはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらが向いているかは投資家のリスク許容度や経済状況によって異なります。固定金利は返済額が一定のため、長期的な資金計画を立てやすく、金利上昇リスクを避けたい方には向いています。一方、変動金利は当初の金利が低いため返済負担を抑えやすいものの、将来的に金利が上昇すればその分返済額も増え、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。
初めての投資や長期保有を前提とする場合は、金利変動の影響を受けにくい固定金利が安心でしょう。なお、一定期間は固定でその後に再選択できる「固定期間選択型」など、状況に応じて選べる商品もあるため、複数のローンタイプを比較して自分に合ったものを選ぶことが大切です。