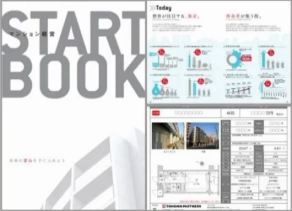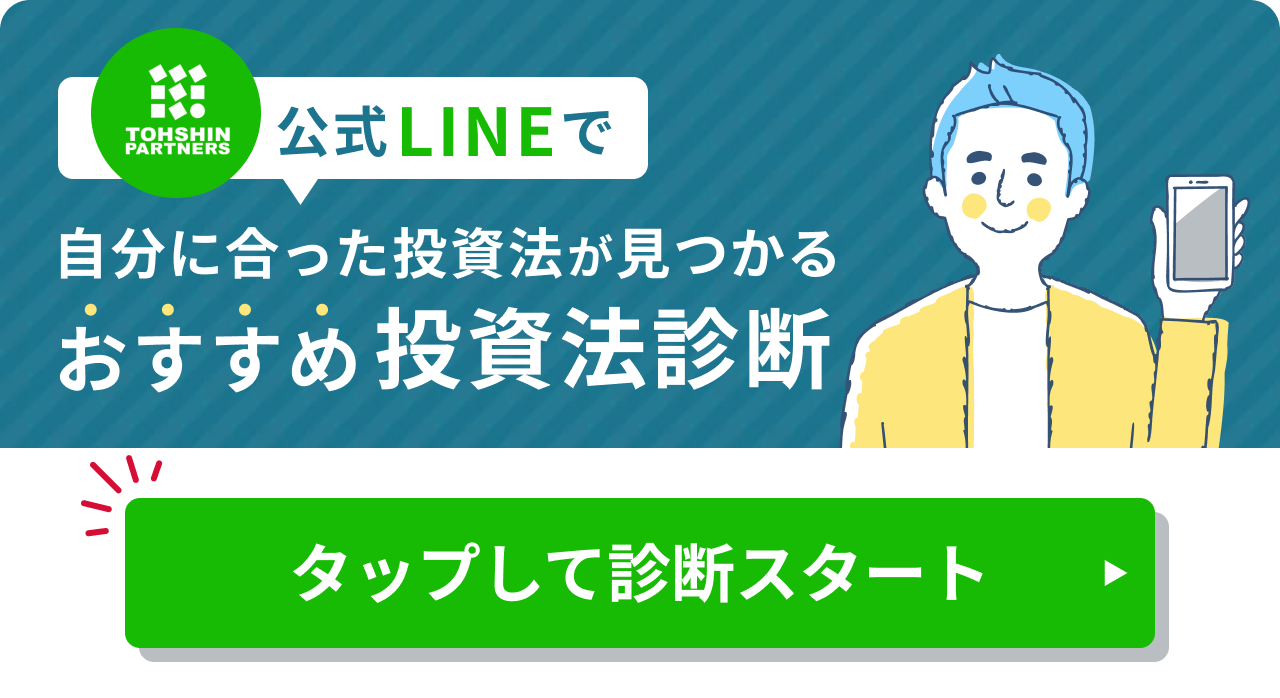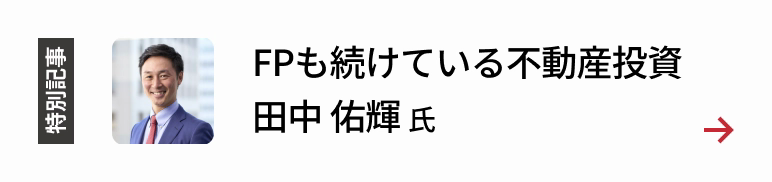- 不動産投資の基礎知識
初心者が知っておくべき不動産投資の現実|やめたほうがよい人の特徴も

不動産投資は魅力的な資産形成の手段として注目を集めていますが、実際には多くの落とし穴が存在します。この記事では、これから不動産投資を始めようと考えている方へ、リスクとメリットを正しく理解するための情報をお伝えします。現実的な視点で不動産投資と向き合うことで、より賢明な投資判断ができるため、ぜひ参考にしてください。
不動産投資で利益を得る仕組み

不動産投資では「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」という2つの方法で利益を得られます。これらの方法は、それぞれ異なるリスクとリターンの特徴を持っています。まずは、これらの収益構造を十分に理解し、自身の投資目的に合わせて選択しましょう。
家賃収入でインカムゲインを得る
インカムゲインは、物件を購入して入居者から家賃を受け取る収益方法です。たとえば、2,500万円のマンションを購入し、月額10万円で賃貸に出した場合、年間120万円の家賃収入を得られます。このように毎月一定の収入が見込めるため、長期的な資産形成に適しています。
また、インカムゲインの大きなメリットは、不動産価格の変動に左右されにくい点です。不動産価格が変動しても家賃自体は大きく変動しないため、安定した収益を得られます。さらに、減価償却費を活用することで節税効果も期待できます。
一方で、空室リスクや建物の維持管理費用が必要になることも考慮しなければなりません。物件の立地や管理会社の選定が重要なポイントとなるため、慎重な検討が必要です。
物件の売却でキャピタルゲインを得る
キャピタルゲインは、物件価値の上昇を見込んで売却益を得る方法です。たとえば、2,500万円で購入した物件が、数年後に3,000万円で売却できれば、500万円の売却益を得られます。
この方法の魅力は、短期間で大きな利益を獲得できる可能性がある点です。特に再開発が予定されているエリアや、インフラ整備が進む地域では、大きな値上がりが期待できるでしょう。
ただし、不動産市況の変動はリスクであり、物件価値が下落する可能性もあります。そのため、地域の将来性や不動産市場の動向を見極める目利き力が必要です。
初心者が知っておくべき不動産投資の現実

初心者が知っておくべき不動産投資の現実は、以下のとおりです。
- サラリーマンがカモにされることがある
- ローンを利用する場合、キャッシュフローは当初マイナスから始まることも多い
- 物件によっては節税効果が低い
- 空室が続くリスクがある
それぞれ見ていきましょう。
サラリーマンがカモにされることがある
不動産投資の世界では、投資経験の浅いサラリーマン投資家が狙われやすい傾向にあります。特に問題となるのは、投資経験の少なさを利用され、実態より高額な物件を購入させられるケースです。
たとえば、相場より2割ほど高い物件を「値上がり確実」と説明され、無理なローンを組まされたり、「満室保証」を謳いながら、実は相場より低い家賃設定で契約を迫られたりするケースがあります。また、立地が悪い物件を「将来性がある」と偽って販売されることもあります。
このような被害を防ぐためには、不動産投資の基礎知識を身につけ、複数の不動産会社から提案を受けることが重要です。
▼サラリーマンがカモにされる事例
サラリーマンは不動産投資のカモにされる?危険な理由と成功のポイント
ローンを利用する場合キャッシュフローはマイナスから始まることも多い
キャッシュフローがマイナスになる物件とは、毎月の家賃収入よりも、ローンの返済額や管理費などの支出が上回る状態の物件です。
たとえば、月々の家賃収入が10万円であるのに対し、ローン返済が8万円、管理費が2万円、修繕積立金が1万円という場合、毎月1万円の赤字が発生します。
しかし、このような状況は、決して特殊なケースではありません。
重要なのは、マイナスキャッシュフローを想定した資金計画を立てることです。数年間は毎月の持ち出しが必要になることを前提に、十分な余裕資金を確保しておく必要があります。また、将来的な金利上昇や空室リスクも考慮に入れた計画を立てましょう。
不動産投資は短期的な収益ではなく、10年、20年という長期的な運用を前提とした投資だということを理解しておくことが重要です。
物件によっては節税効果が低い
不動産投資の節税効果は物件の特性によって大きく異なる点に注意しましょう。築古物件の場合、一般的に建物価格が新築より低く見積もられるため、一見すると節税効果が低いように思えます。しかし、残存耐用年数が短いため、その分短期間で減価償却を行えるというメリットがあります。
一方で、都心のワンルームマンションなどは物件価格に占める土地価格の割合が高く、その分建物の減価償却費が少額になりがちです。また、耐用年数が長いため、年間の減価償却費も小さくなります。
このように、節税効果を考える際は単に「築古か新築か」だけでなく、以下の要素を総合的に判断する必要があります。
- 建物価格と土地価格の比率
- 残存耐用年数
- 年間の減価償却費の大きさ
- 自身の所得状況と必要な節税額
物件選びの際は、これらの要素に加えて、立地や将来性、賃料収入なども含めた総合的な判断が重要です。
空室が続くリスクがある
不動産投資において、空室リスクは収益性を大きく左右する問題です。立地条件の悪い物件や、周辺の賃貸需要が少ない地域の物件では、空室が長期化する可能性が高くなります。
空室が続くと家賃収入が得られない上に、固定資産税や管理費などの支出は継続して発生するため、大きな損失につながってしまいます。
このリスクを軽減するためには、入居者ニーズの高いエリアを選び、物件の適切な維持管理を行うことが重要です。また、周辺相場に見合った家賃設定や、営業力の高い管理会社の選定も効果的な対策です。
不動産投資には多くのメリットもある

不動産投資にはリスクが存在しますが、以下のようなメリットもあります。
- 相続税の節税効果がある
- 生命保険の代わりになる
- 年金の代わりになる
- インフレ対策になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続税の節税効果がある
不動産投資による相続税対策は、多くの投資家が注目している方法です。不動産は現金や預貯金と異なり、相続税評価額が時価よりも低く評価される特徴があります。一般的に、土地は路線価で評価され、建物は固定資産税評価額が基準となりますが、これらの評価額は通常、時価より低く設定されています。
たとえば、時価1億円(土地7,000万円、建物3,000万円)の不動産を相続し、相続税評価額が以下のように算出されたとしましょう。
- 土地:路線価による評価で時価の約80%
- 建物:固定資産税評価額で時価の約60%
この場合、相続税評価額は「7,000万円×80%+3,000万円×60%」で7,400万円となります。
さらに、不動産のなかでも、相続税の節税効果は異なります。相続税対策に向いている不動産の特徴は以下の通りです。
- 都心の優良物件
- 賃貸用の区分所有マンション
- 小規模宅地等の特例が適用可能な物件
都心の優良物件は、市場価格と評価額の差が大きく、節税効果が高くなります。区分所有マンションは、管理が比較的容易で相続後の運用がしやすい点が特徴です。また、小規模宅地等の特例が使える物件は、評価額を最大80%減額できる可能性があります。
生命保険の代わりになる
不動産投資には生命保険の代替機能があります。投資用物件をローンで購入する際には通常、団体信用生命保険に加入します。この保険は、ローン債務者が亡くなった場合や高度障害となった際に、ローンの残債が免除される仕組みです。
遺族には、借金のない不動産と毎月の家賃収入が残されます。これにより、遺族の生活を経済的に支える効果が期待できます。また、生命保険料を別途支払う必要がなく、家賃収入から返済できるのも魅力的でしょう。
さらに、不動産価値の上昇による資産価値の増加も期待できます。生命保険は満期や解約時の受取額が確定していますが、不動産投資では市場価値の上昇による追加的な利益も見込める可能性があります。
年金の代わりになる
不動産投資からの家賃収入は、老後の年金代わりとして活用できます。公的年金の支給額に不安を感じる方にとって、安定的な収入源となり得るでしょう。賃貸物件からの収入は、入居者がいる限り継続的に得られます。
また、年金と異なり、受給開始年齢の制限がありません。若いうちから不動産投資を始めることで、早期に安定収入を確保することが可能です。物件の立地や管理状態を適切に保つことで、長期的な収入が期待できます。
インフレ対策になる
不動産はインフレに強い資産として知られています。物価上昇に伴い、不動産価値や賃料も上昇する傾向にあるためです。現金や預貯金は、インフレによって実質的な価値が目減りしますが、不動産は実物資産として価値を保ち続けます。
実際、好景気による物価上昇局面では、不動産価格も上昇する傾向にあります。また、賃料も物価上昇に連動して増額改定が可能です。このように、不動産投資はインフレヘッジ(対策)として機能することが期待できます。事実、多くの投資家が資産防衛の手段として不動産投資を選択しています。
不動産投資はインフレ対策になる3つの理由|関係性や注意点も解説!
不動産投資をやったほうがよい人の特徴

ここからは、不動産投資のメリット・デメリットを踏まえて、不動産投資をやったほうがよい人の特徴を紹介します。
- 安定した収入がある会社員や公務員
毎月の収入が安定している方は、不動産投資ローンの審査が通りやすい傾向にあります。また、将来の返済計画も立てやすく、金融機関からの信用も得やすいでしょう。特に大企業の正社員や公務員は、安定性の面で高い評価を受けます。 - 資産形成に対して計画的な性格の人
不動産投資は長期的な視点が必要です。月々の収支管理や修繕計画、将来の売却なども見据えて、計画的に運用できる方が向いています。感情的な判断ではなく、数字やデータに基づいて冷静に判断できる性格も重要です。 - 情報収集や勉強を継続できる人
不動産市場の動向や税制の変更、管理会社との付き合い方など、常に新しい知識を吸収する必要があります。セミナーや書籍で学んだり、専門家に相談したりして、積極的に知識を深められる方が成功しやすいでしょう。 - 一定の金融資産を持っている人
予期せぬ修繕費用や空室期間の家賃収入減少など、不測の事態に対応できる資金的な余裕が必要です。最低でも、数百万円程度の金融資産を持っていることが望ましいといえます。
このような特徴を持つ方は、不動産投資で成功する可能性が高くなります。ただし、これらの条件を完璧に満たす必要はありません。ご自身の強みと弱みを理解した上で、投資を検討してみましょう。
不動産投資をやめたほうがよい人の特徴

ここからは、不動産投資のメリット・デメリットを踏まえて、不動産投資をやめたほうがよい人の特徴を紹介します。
- 金融資産や現預金に余裕がない人
手元資金が少ない状態での不動産投資は非常に危険です。予期せぬ修繕費用や空室による収入減少に対応できず、資金繰りが悪化する可能性があります。また、ローン返済の負担も大きくなり、生活に支障をきたすリスクもあるでしょう。 - 投資に関する勉強を積極的にしない人
不動産投資では、物件選びから資金調達、税務、入居者管理まで、幅広い知識が必要になります。こうした知識を身につける意欲がない方は、判断を誤って損失を被る可能性が高くなります。 - リスクに対して過度に不安を感じる人
不動産投資では、空室や家賃滞納、物件価値の下落など、様々なリスクが存在します。これらのリスクに対して過度に不安を感じる方は、精神的なストレスが大きくなり、冷静な判断ができなくなる可能性があるでしょう。 - 収入が不安定な人
フリーランスや収入の変動が大きい職種の方は、安定した収入が見込めないため、ローンの返済が困難になるリスクがあります。金融機関からの融資も通りにくく、条件も不利になりやすいでしょう。
このような特徴に当てはまる方は、まずは資産形成の基礎を固めることを優先し、その後で不動産投資を検討するのが賢明です。
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
まとめ

不動産投資には、相続税対策や生命保険・年金代わりなど、多くのメリットがありますが、誰にでも向いているわけではありません。安定した収入があり、計画的に資産運用ができる方には向いていますが、資金的な余裕がない方やリスク耐性の低い方は避けたほうがよいでしょう。
不動産投資を始める前に、自身の経済状況や性格特性を見極め、メリット・デメリットを十分に理解することが大切です。必要に応じて専門家に相談し、慎重に判断しましょう。